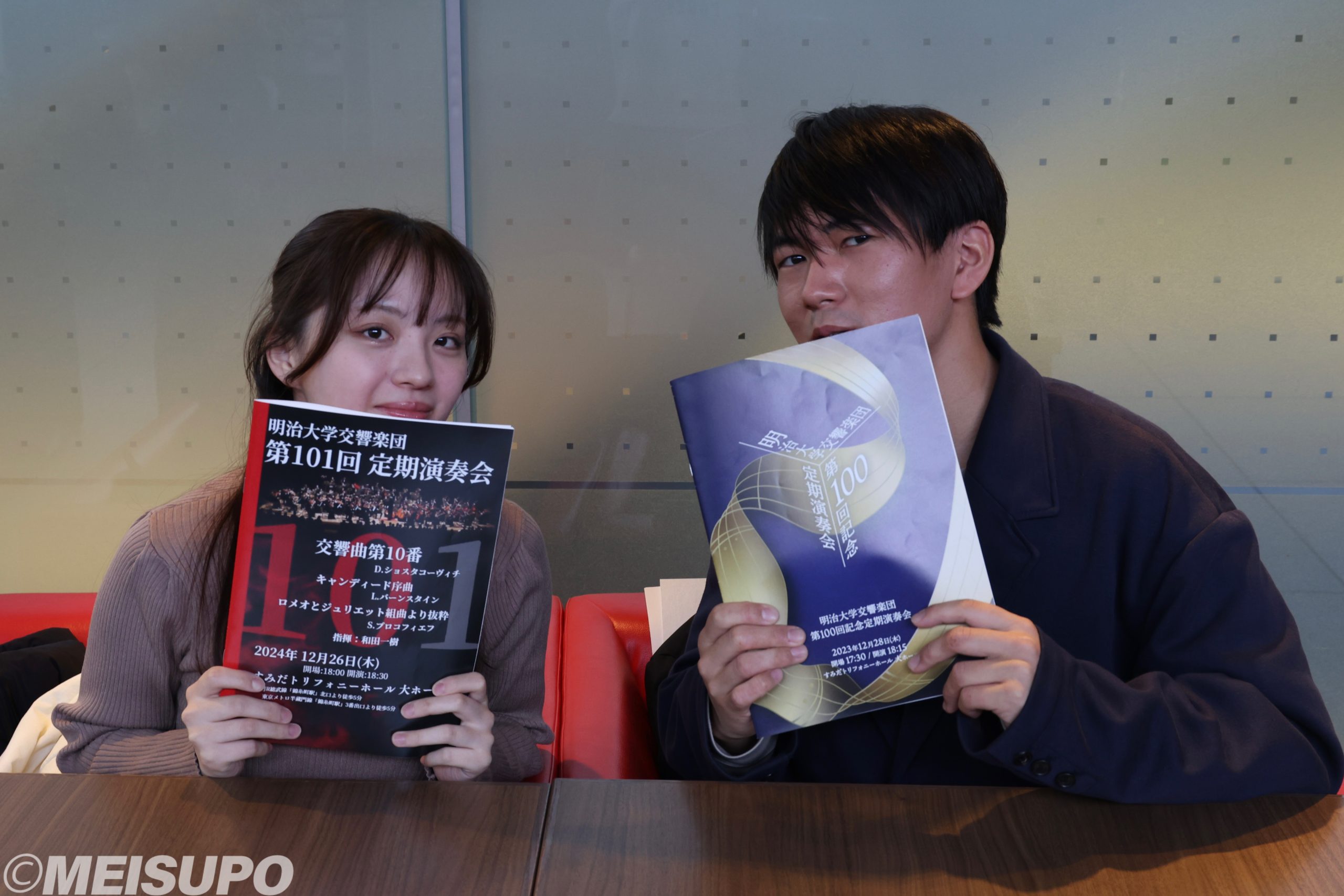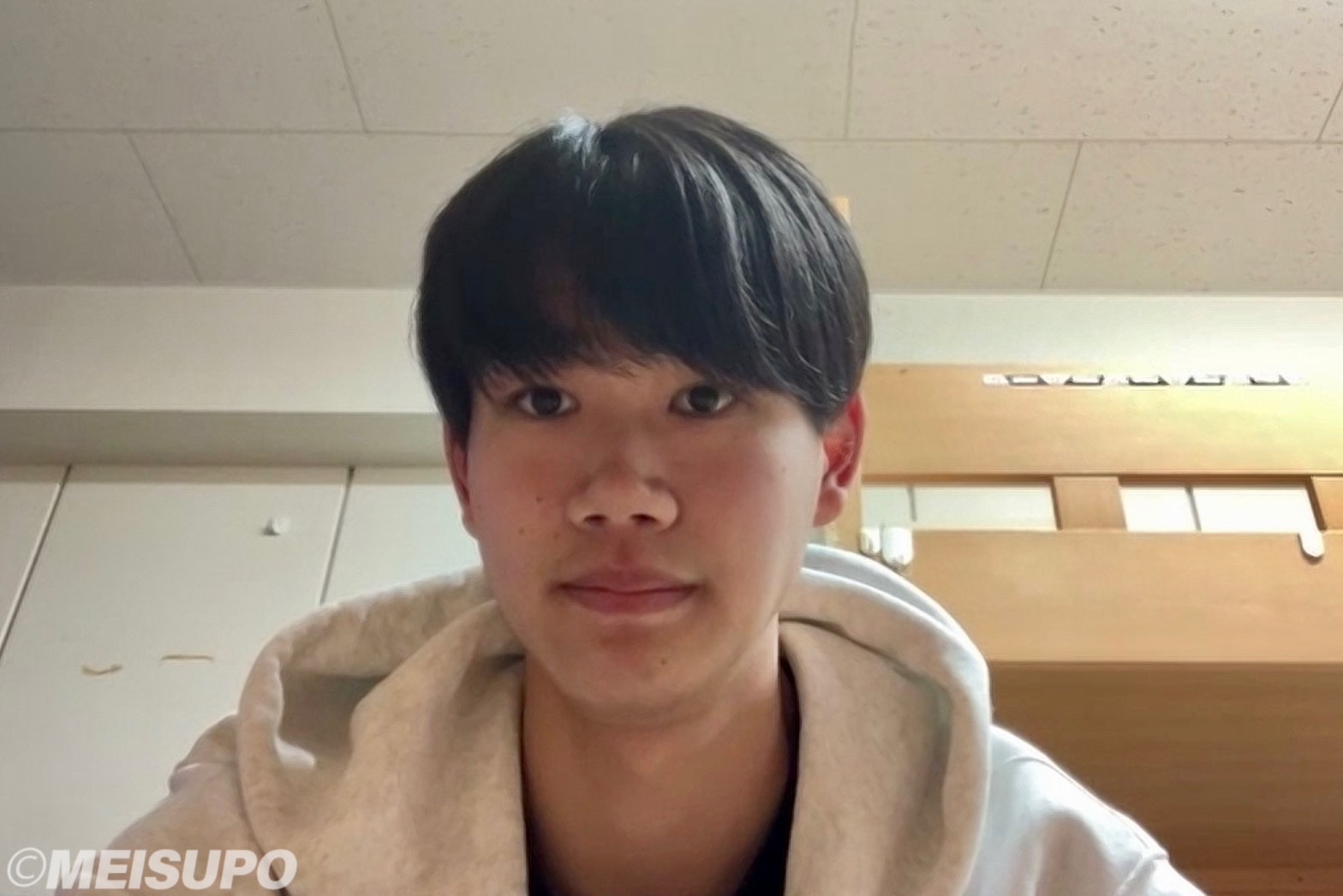eスポーツは学生スポーツになるのか? ①eスポーツの魅力とは /NEW WAVE ~学生スポーツへの可能性~(2)
eスポーツは果たして学生スポーツになる可能性があるのか?今回は2018年にeスポーツの振興を目的に設立された日本eスポーツ連合の広報・戸部浩史氏に取材を行った。
第1弾は近年注目を集めているeスポーツの魅力に迫っていく。
※この取材は9月29日に行われたものです。
2022年アジア競技大会(開催は来年度に延期)において正式種目と認定され、情報化時代の新たなスポーツとしてますます脚光を浴びるeスポーツ。瞬発力や戦略性がシビアに求められるのが特徴的な競技だが、一方で新しい生活様式に合う競技としても現在注目を集めている。eスポーツは『エイジ(年齢)レス』『ジェンダー(性別)レス』『ハンディキャップ(身体的な差異)レス』『エリア(環境や場所)レス』という四つの特徴を有しているが、新型コロナウイルスがまん延した際に着目されたのが『コンタクト(接触)レス』だ。「相撲などのスポーツ競技の中には肉体がぶつかり合うものがあるが、eスポーツは肉体的な接触がほとんどない。接触による怪我の可能性は極めて低く、安全を担保しながら行うことができる」。離れていてもオンラインで競技することが可能で、ここが通常のスポーツとは大きく違う点である。

(『第18回アジア競技大会』ではデモンストレーション競技としてeスポーツが行われた)
そして、それに付随してコミュニケーション能力が強化できるのが魅力的なところ。eスポーツにはチームとして戦う大会や協力してクリアを目指すゲームタイトルも多いため、コミュニケーションを取ることが必要になってくる場合が多い。こういった特徴に目を付け、最近では高齢者の福祉施設におけるコミュニケーションツールとしてもeスポーツが取り入れられている。「高齢者の中には普段から他者とのコミュニケーションが少ない人もいる。『頑張れ』と応援したり、『危ない』と声を発するだけでも脳の回復に貢献するケースがあると聞いている」。福祉利用ではないが、『エイジレス』の特徴を活かしたケースとして、秋田県では日本初のシニアプロゲーマーチームが活動をしている事例もある。
過疎地域や隔離場所であったとしても継続してコミュニケーションを取れることから、地域振興に役立てようとする動きも。2019年に茨城県で初めてのeスポーツ全国大会が開催されると、各地でeスポーツを用いたイベントが急増。地域に元から根付いている産業と掛け合わせることで、さらに活性化できる期待がある。実際に海外では都市対抗のリーグ戦が設置されるなど、Jリーグなどと同じようにeスポーツのクラブチームが創設されるケースも存在しているほどだ。海外では他のスポーツ競技と同様の扱いを受けていることも多く、これからの日本もさらに地域と密接に関わっていくことが予想される。

(eスポーツイベントが全国で開催される先駆けとなった『全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2019 IBARAKI』)
老若男女、身体能力の差などを取り払ってプレーすることができる魅力があるeスポーツ。その市場規模は2018年の約48億円から年々増加し、2023年には1700億円を突破すると予想されている。『コンタクトレス』という特性も加わり、ウィズコロナの時代が続く中でも新たなコミュニケーションツールとしても期待ができそうだ。
[菊地秋斗]
関連記事
RELATED ENTRIES