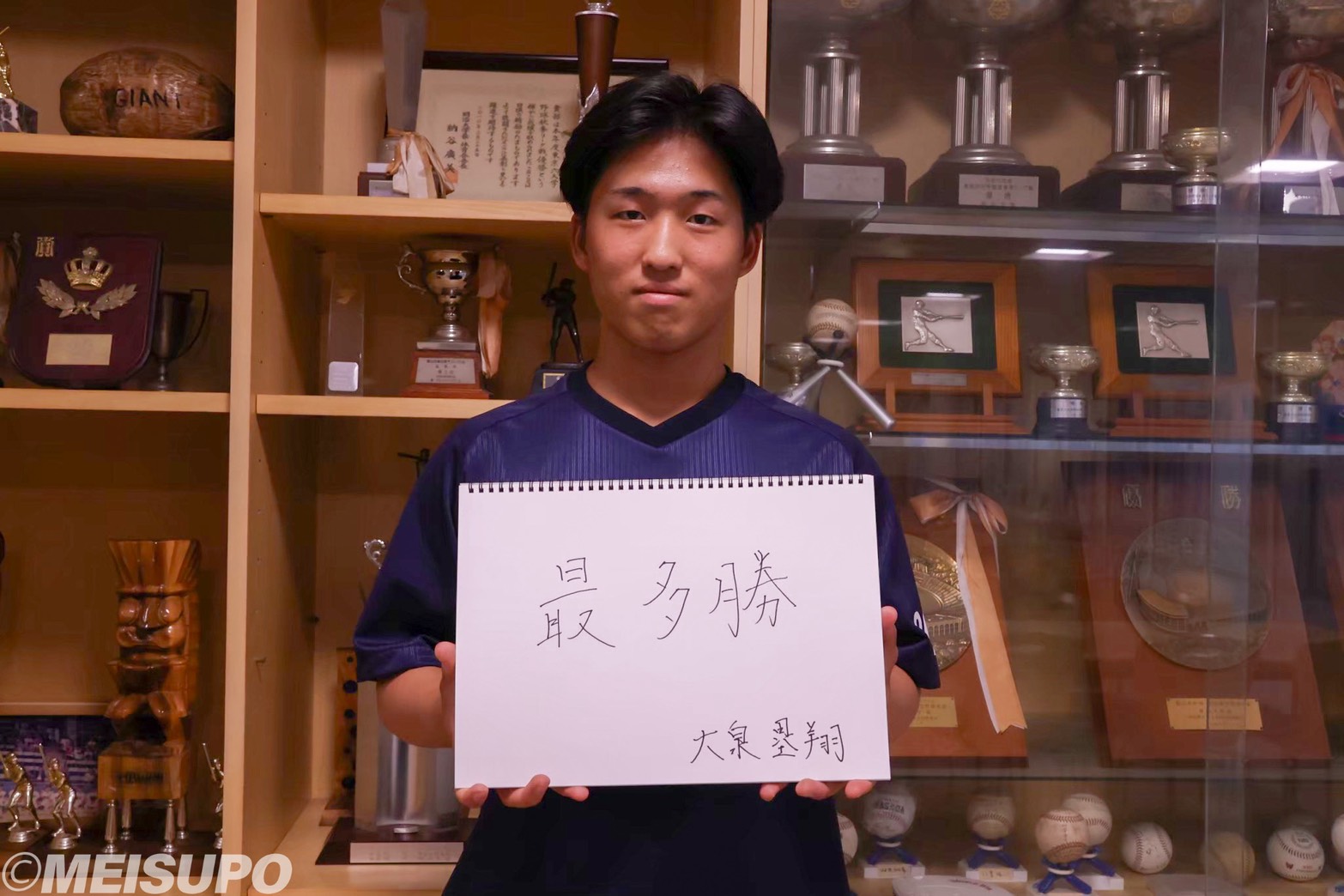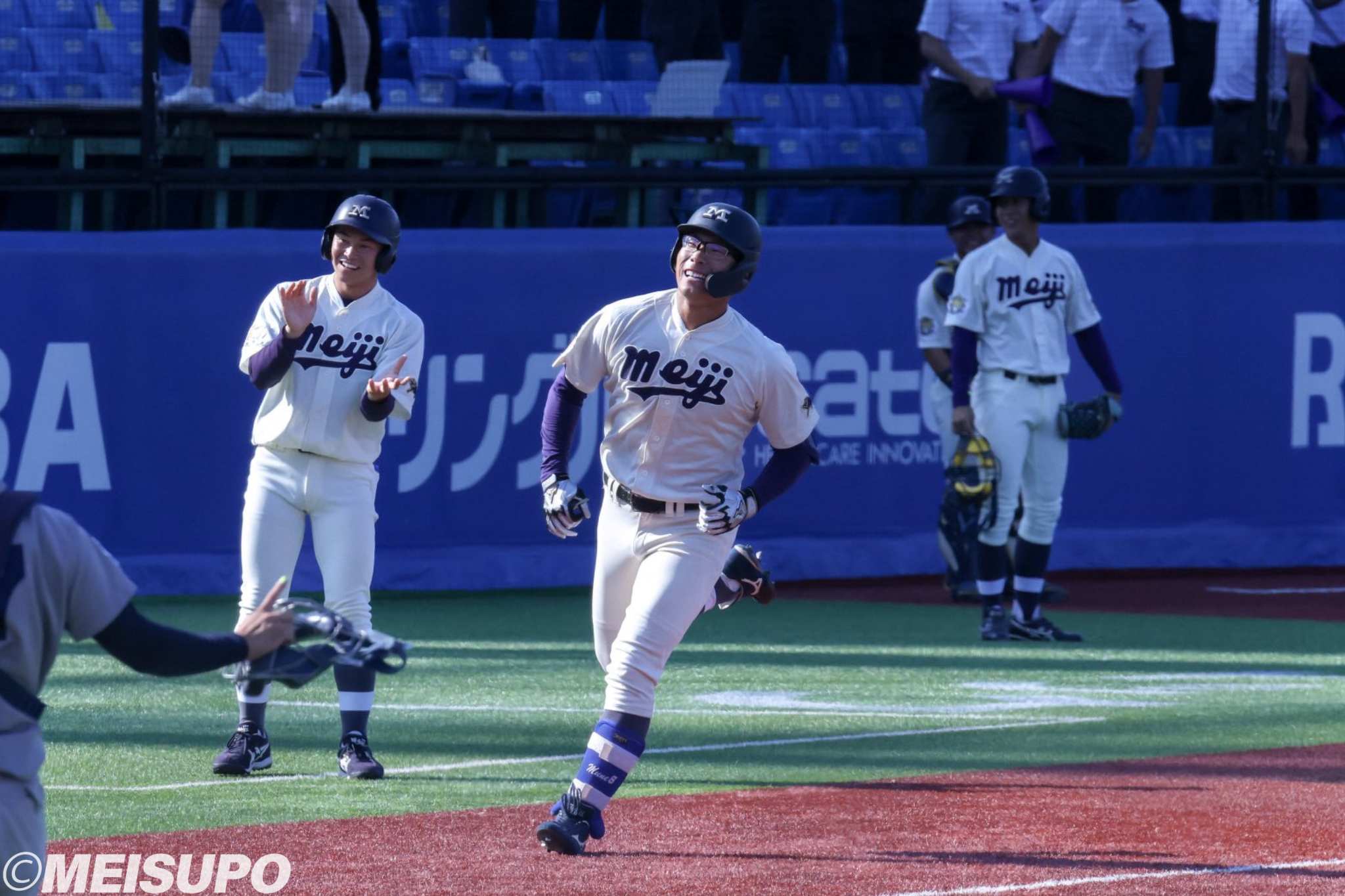(44)特別インタビュー 広澤克実氏

(この取材は8月28日に行われました)
広澤克実氏(昭60文卒)
――東京六大学野球の解説を務められている広澤さんの現在のご活躍について教えてください。
「大学の新聞部の取材で言えるのはまず中学生の硬式野球、ポニーリーグの理事長をやっています。明治との関係で言えば、硬式野球部OB会の理事で、技術指導員を務めていますよ」
――春季リーグ戦は早大が制しました。
「春はやはり早稲田の選手が非常に躍動したということですね。小宮山監督(早大)にとっても優勝が空いていたので、彼の監督としての評価やその他の選手も含めて早稲田が目立った春だったかなと思いますね。(2位の明大との勝敗を分けたポイントはどこであったとお考えでしょうか)日大三高出身の安田投手(早大)の投球ではないでしょうか。彼が吉永くん(早大卒、JR東日本などで活躍)に教わったというチェンジアップあるいはシンカー、これが全てだったかな。明大対早大の1回戦の9回裏1死満塁で登板して最初に打席に立った横山(陽樹外野手・政経4=作新学院)も初めて見るボールだっただろうし。他の選手も少し違って見えただろうと思います。人間は記憶という部分で、特にボールの軌道や減速力などの面で記憶が左右するものと全く左右しないものがバッティングにあります。変化球は記憶というか残像が脳の中にない状態であのシンカーを見せられたら難しい話だと思いますね。吉永くんのシンカーは私も知っていて、当時の明治もシンカーと同じ軌道から来るカーブに翻弄(ほんろう)されました。ただし秋は分かりません。変化球の残像と速いボールに対するイメージが残っていればまた違った形になると思います」
――続いて秋季リーグ戦について、慶大・清原選手は注目を集める選手の一人です。
「バッターには得意不得意があるので、インコースが強いとアウトコースが弱いとか、ストレートに強いと変化球が弱いとか。高めが強いと低めが弱いとか、相対的になるものがあって、両方打てる選手がいい選手だということになります。そういう意味では彼はまだいいところと悪いところがはっきりしていますね。なので弱いところを攻められたら辛いと思います。『清原和博さんの息子』ということを置いて選手として考えたときに、どうなんだろうというところはある。六大学の慶應の4番バッターとして考えるとまだまだです。ですが人間、恥文化というのがあって注目されると『恥をかきたくない、みっともない姿を見せたくない』というエネルギーが生まれてそれが成長をさせてることもあるかもしれません。春の段階で見ればですが、お父さんに習ったり、恥ずかしい思いをしたくない、いろんな声援に応えたいというエネルギーが彼を成長させていれば、非常に楽しみになります」
――母校・明大の宗山塁主将(商4=広陵)についてはいかがでしょうか。
「宗山に関しては3年生の途中からバッティングを崩しました。4年生になってからもアンラッキーなケガがあって、私からすれば先ほどの清原くんと一緒で評価を落とさないくらいの成長をこの夏にしてほしいと思います。人間正しいことばかりをやれるわけではありませんよね。経験はいい経験も大事ですが悪い経験も大事で、これは恋愛と一緒ですよ(笑)。ドラフト1位だとかいろんな評価や報道があった3年生の途中からのこの1年半というのは彼にとっては大変だったと思います。評価に追いつこうとして一生懸命いろいろなことを取捨選択しながら練習した中で間違った選択をしたこともあるかもしれません。これはプロの選手でもそうです。ですが悪いことが分かって初めていいことが見つかることもあるので、彼には1年半苦労した分評価に追いつけるようなバッティングをしてほしいと思っています」
――日々のご解説の中で小島大河捕手(政経3=東海大相模)の打撃を高く評価されています。
「小島は打つことも捕って投げることも能力があって、打つことに関しては天才的です。弱点としては2つあって、まずキャッチャーとしての配球で、もう一つは少し非力なことですかね。芯に当たればスタンドには入るのですが、もっとパワフルになる必要があります。小島は将来150キロを打ち返す世界に行くはずなので、それならパワーが欲しいです。トレーナーの方に『やっとちゃんとウエートをやり出した』と聞いています。あと心配なのは配球だけで、打つことに関しては心配していません」
――明大・田中武宏監督をはじめ、リーグの指導者には何を求めますか。
「学生野球なので、プロ野球と違って教育の側面があります。強ければいいわけではないし、反対に教育できてればいいわけでもないんですが、昨今は一部で間違った考え方が広まっているように思います。教育の現場だから教育優先だと思っている人が多くいます。例えば例が悪いかもしれませんが家族思いのお父さんがいたとして、家族を大事にするけども収入がないとします。反対に収入はあるけど家族を大事にしないお父さんがいたとします。これどっちもおかしいですよね。収入もあり家族も大事にするのが理想です。であれば大学野球も両方必要です。教育もあってそこに勝利・優勝があるわけで、どちらが優先、という話ではなくて同じ位置にあります。教育と勝つことは同じ位置にあって、いい教育ができてそして優勝すること。これが一番ですよね。これは各大学の監督にお願いしたいですね。勝つことと教育は同じレベルにある。これが理想だと思っています」
――戦術的には、小技を多用する小さい野球が文化としてリーグに根付いているように感じます。
「まあバントをすることもエンドランをすることも構わないのですが、目的は点を取ることです。その手段として例えば盗塁があったり、バントがあったり、エンドランがあったり、またはホームランがあったりします。手段と目的というものがあって、バントが目的になってはいけません。点を取るために手段としてバントをするのは良いのですが、例えばダブルプレーを怖がってバントするのはもってのほかです。点を取るための手段としてなら良いのではないでしょうか」
――大学野球の解説者を務める中で何を意識されているのでしょうか。
「正直であることです。あとは耳障りの良い言葉ばかりを使わないということですね。例えば早稲田と明治の試合があったとして、ファンの方からは私が早稲田を応援するがわけないと思われていると思うんです。『早稲田頑張れ』なんて言ったら綺麗事ですよね。明治戦は明治を応援しています。ただし明治だろうがそれ以外の大学だろうがいいプレーには必ず拍手をしようとは思ってますし、悪いプレーは悪いと言おうとは思っていますよ」
――以前の放送の中で『野球を楽しんでやろうなんて大間違い』というご発言がありましたが、真意を教えてください。
「これは明治の話で、野球部の方針として明治と書いてある以上、楽しいと思うのは優勝した瞬間で良いと思っています。そうじゃないなら楽しいなんて思ってやって欲しくない。部員が140数人いてね、ベンチ入りが25名。となれば100人以上がベンチにも入れません。そういう人の思いや先輩方の存在などいろいろなものを考えてベンチに入って行った時に、楽しいと思ってやってもらいたくないんです。スクールカラーもあります。他の大学は良いのですが、明治大学に限っては楽しいとは思って欲しくないですし、十分にプレッシャーを感じてやる中でどうやって自分の力を出すか。〝楽しい野球〟は河川敷でやって欲しいですね。試合に出る責任を感じれば、自ずと楽しいなんて思わないと思います」
――東京六大学は注目度や規模という面においては特殊なリーグだと思われますが、そのことをどう解釈されているのでしょうか。
「『なんであの6チームしか戦ってないようなところで天皇杯なんてあるんだ?』なんて言う人もいるのですが、元々は大正時代に摂政杯をいただいている歴史があります。ちなみに他に摂政杯をいただいた競技としてはゴルフがあります。その後、昭和になって1947年に天皇杯を下賜されました。戦後、当時すごく人気があった六大学の人は家族や親戚が戦死されて、でもそんな中で希望の光を一つでも、復興のために少しでも役立ってほしいと。そんな思いで下賜されたんですよね。摂政杯も天皇杯も下賜された競技は六大学しかないのではないでしょうか。サッカーなど他の競技はそれを管轄する団体に与えられています。ですが野球には全体を管轄する団体はありません。ということはそもそも野球に今、天皇杯を預けるところはないということになります。下賜された理由さえ知らないくせに天皇杯がうんぬんって言うのは見当違いで、昭和天皇から摂政杯も天皇杯もいただいているので、これを変えられるのは昭和天皇しかいません。立川の昭和記念公園に行って直談判してこいという話ですね(笑)。野球の歴史的に言えば、1903年に早稲田と慶應から始まったとするとこの年ってライト兄弟が空を飛んだ年です。その6年後に3校対決ってのがあるのですかね。この時期から始まった歴史というのはプロ野球にも高校野球にもありません。このように歴史というのは他の連盟さんと少し違うところですかね」
――球場に訪れるファンや学生に向けて、見るべきポイントを教えてください。
「どの連盟にも言えることなんだけど、やっぱり自分の母校愛やチーム愛。こういうものが感じられる野球であることですね。六大学はやっぱり伝統。そんなものを受け継いで、感じてほしいですね。いろいろな歴史がある中で、歴史と伝統を背負っているということを感じて欲しいです」
――ありがとうございました。
[上瀬拓海]
※本インタビューは秋季リーグ戦期間中に明治神宮球場で配布する東京六大学新聞連盟合同誌「Big6 Journal」でもお読みいただけます。
関連記事
RELATED ENTRIES