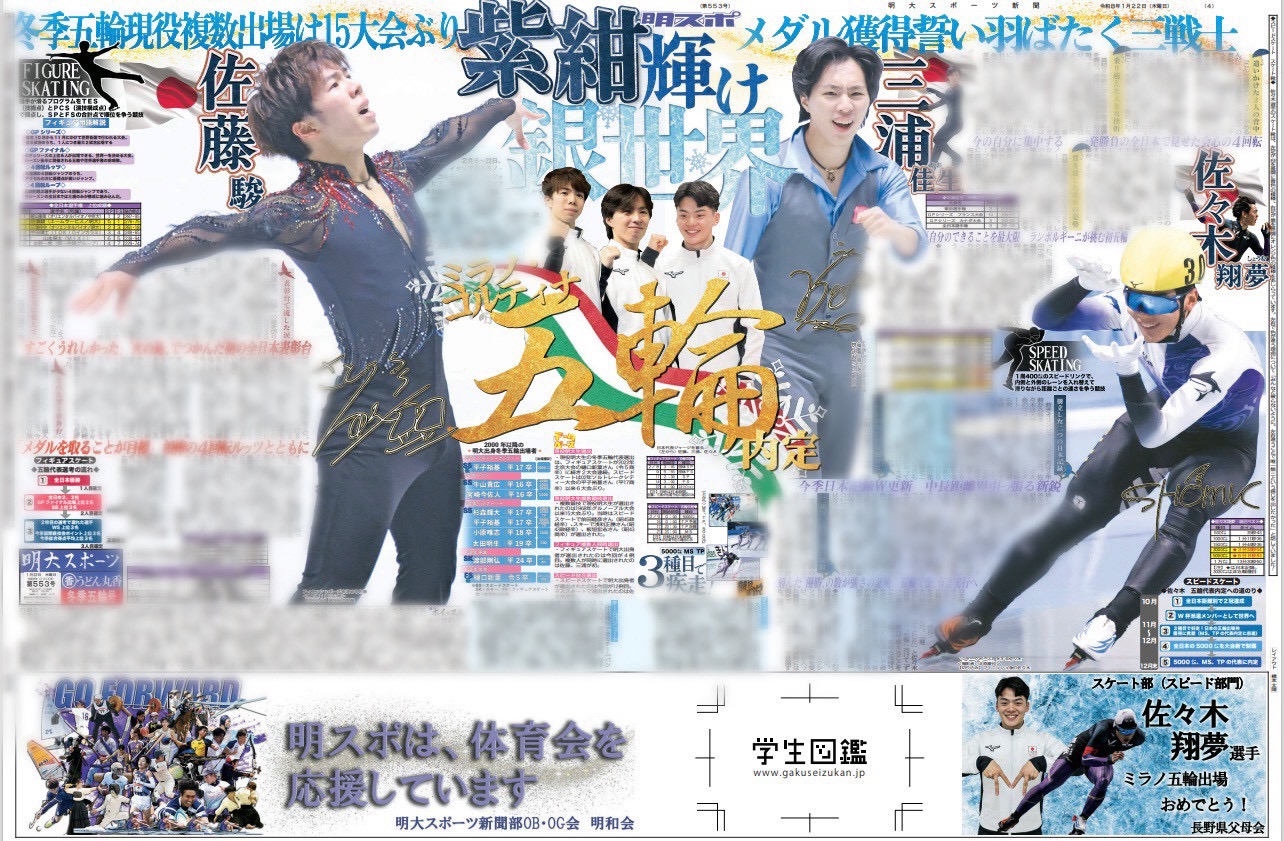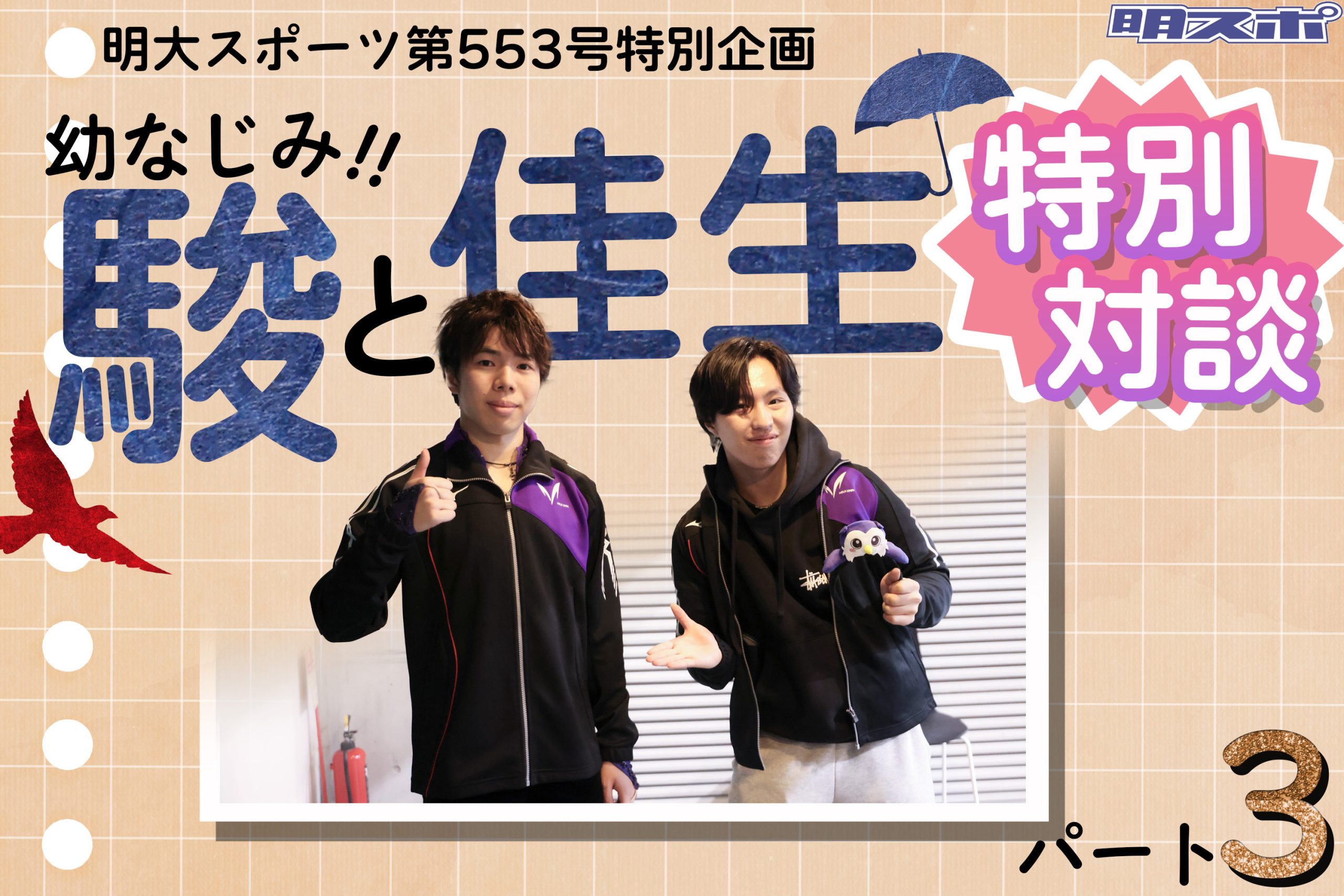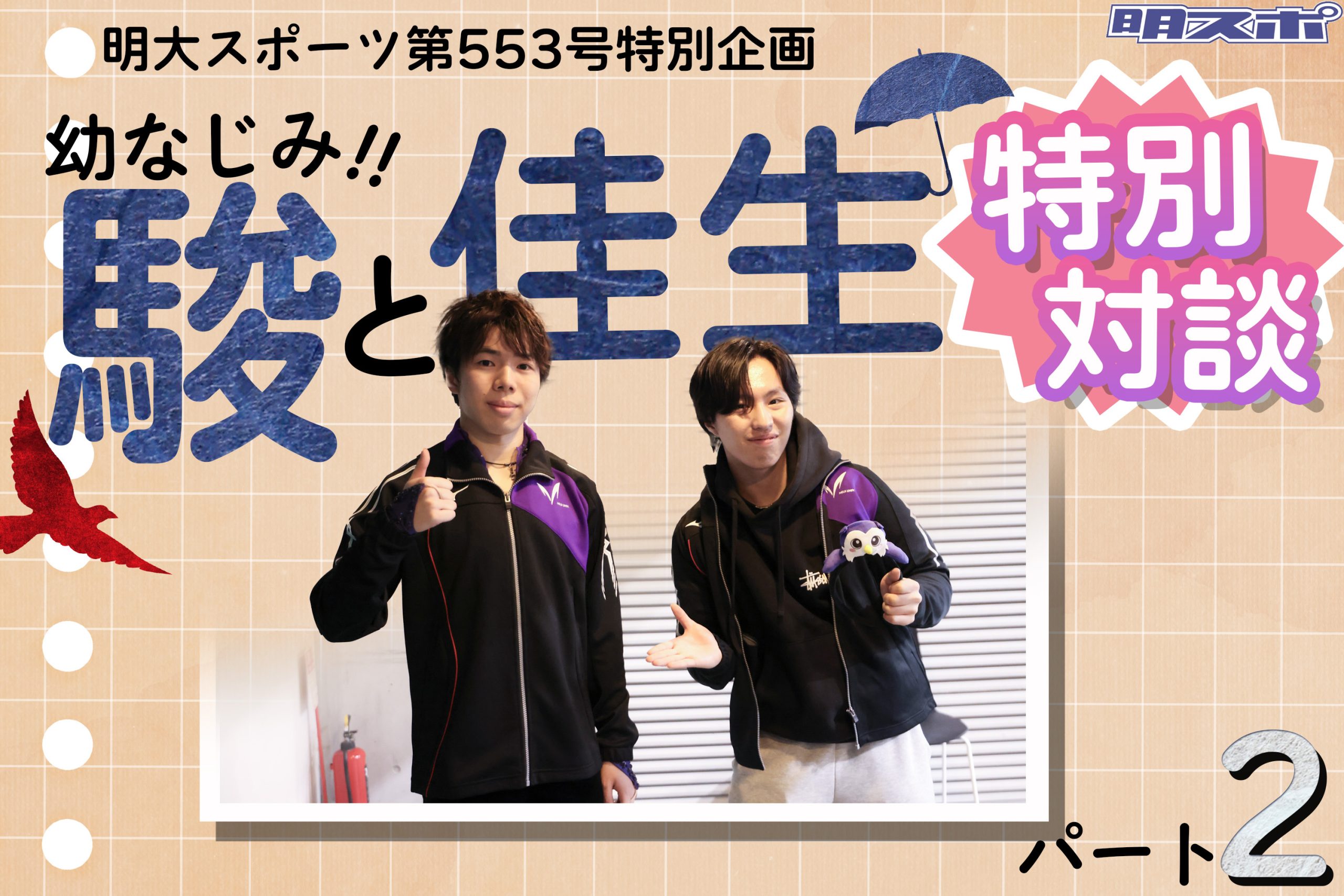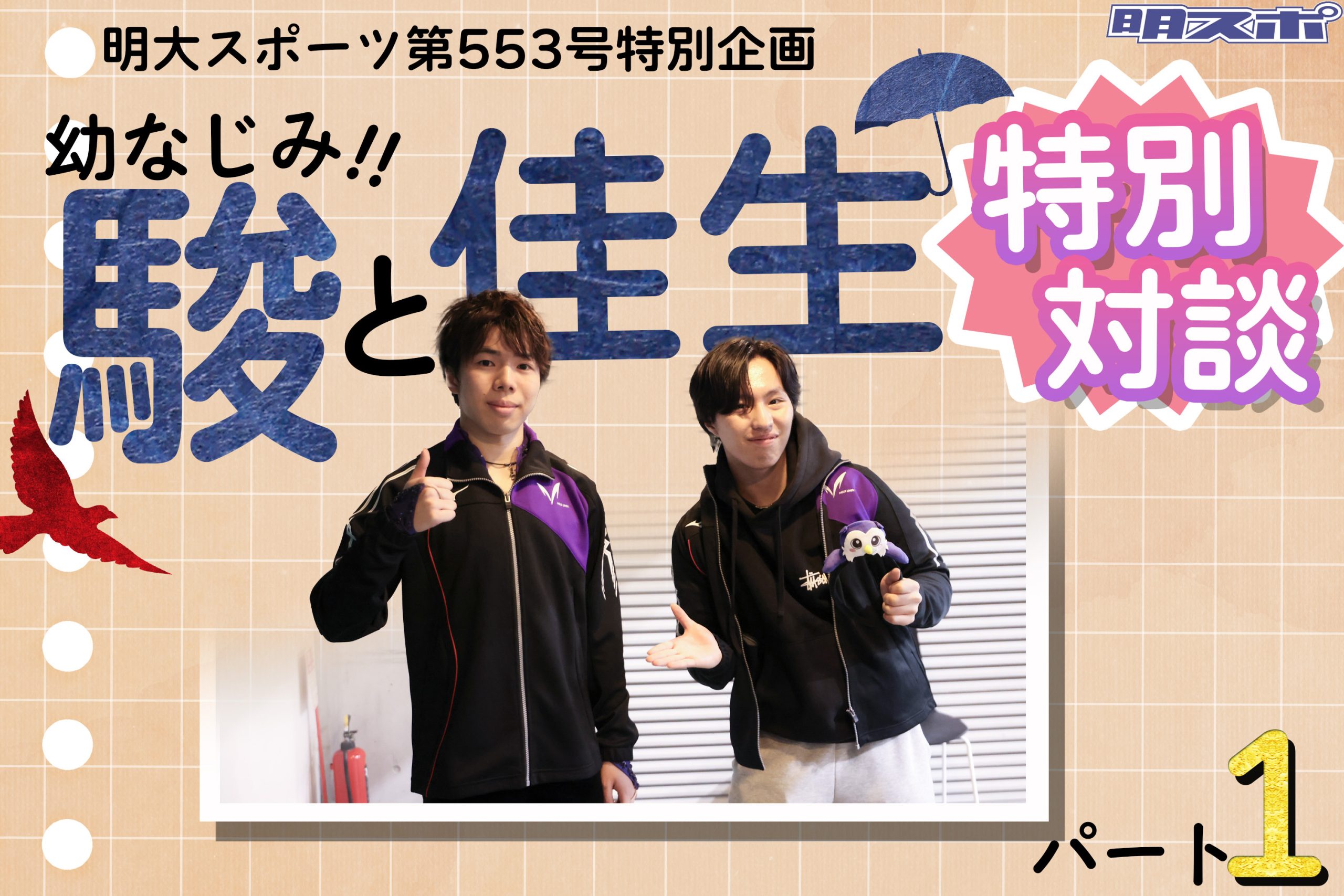明治大学博物館学生広報アンバサダーインタビュー(前編)/オープンキャンパス号特別企画
明大スポーツ第548号(オープンキャンパス号)にて、明治大学博物館を特集しました。今回は、明治大学博物館学生広報アンバサダー(以下、アンバサダー)の木下奈映さん(文3)、上村菜摘さん(国際2)、長屋佳奈さん(文2)、津島聖也さん(情コミ2)にお話を伺いました。
(このインタビューは6月24日に行われました)
――博物館の概略を教えてください。
津島 「明治大学博物館の歴史は、1929年につくられた刑事博物館が始まりとされています。1951年、商品陳列館がつくられ、続く1952年には考古学陳列館も開設されました。そして、2004年4月に、この3つの博物館を統合する形で、駿河台キャンパス・アカデミーコモンの地下に現在の明治大学博物館が開館しました。現在、常設展としては、刑事、商品、考古の3部門と大学史展示室で構成されています。また、企画展や阿久悠記念館もあります。一つずつ部門を簡単にご説明すると、商品部門は戦後から現代までの生活や文化経済環境と商品の変化をテーマとして、伝統工芸品を中心とした展示をしています。刑事部門では『法と刑罰』という観点から展示を行っており、特に江戸時代の裁判や刑罰に重きを置いています」
木下 「考古部門は旧石器時代から古墳時代を中心に、明大文学部の史学地理学科考古学専攻がこれまでの発掘調査や学術調査に関わってきた遺跡を中心に時代順に並んでいます。中には重要文化財のものもあり、資料として価値の高いものがそろっている博物館になっています」
津島 「また、大学史展室では、明大の歴史や校友、学生、教職員について詳しく展示されていますのでぜひ見ていただきたいです」
――皆さんのイチオシの展示品を教えてください。
長屋 「茨城県の南塚古墳で発見された埴輪です。その埴輪は矛を持っているのですが、日本唯一のものでおすすめポイントになっています。顔は切れ長の目に深い鼻なので男前な埴輪として知られていて、ぜひ来館した場合には見ていただきたいです」
津島 「私はもともと日本近世史に関心があるので、やはり刑事部門の展示に興味があります。特に処刑で実際に使われた刑罰具の模型は、今の人権や刑罰のあり方について改めて考えるきっかけになる資料になると思います」
上村 「私が好きなのは考古部門の銅鐸です。銅鐸はリニューアルしてから音も聞けるようになっていて、とても推しポイントです」
木下 「私は考古学専攻なのでヘタウマのものが好きです。古墳に馬形土製品があるのですが見た目が恐竜みたいでとてもかわいいのと、博物館には状態のいいものや精巧な造りのものが多いのでより身近に感じられます。ただ見た目がかわいいだけではなくて、実際の社会を垣間見ることができて好きです。あとは、今年から考古部門がリニューアルし触れる展示ができました。特に石器はほぼ実寸大になっていて、学芸員さんの工夫が凝らされているなと思います」
――博物館の良さはどこにあると思いますか。
津島 「いろいろな良さがありますが、大学博物館は大学の研究と社会をつなげる場所としての意義があると思います。また、明治大学博物館は展示品が多いので何人で来ても楽しめる博物館だと思っています」
長屋「明治大学博物館に来館した人が実際に大学に入って、法律学を学んでみたいと思うようになったと言ってくださり、このように大学の研究を通して大学での学びに興味を持ってもらう入り口として博物館の良さがあると思っています」
上村 「私が思う明治大学博物館の良いところは二つあります。一つは考古、刑事、商品という複合型の施設になっていることです。刑事の江戸時代、考古の過去、商品の現代に通じる伝統的工芸品をいろいろな時代にタイムスリップした思いで楽しめます。二つ目は、博物館見学後に階段を上がると考古とコラボしためいじろうのアクリルスタンドなどのグッズが売っていてお家に帰っても楽しめるところがすごい魅力だなと思います」
木下 「私が思う魅力は、3部門だけではなくて、大学史や阿久悠記念館、企画展をやっていることです。大学博物館が昔からあったからこそここまで所蔵品があるということを改めて感じます。また、それぞれの部門に専門の学芸員さんがいらっしゃることです。それぞれの部門にスペシャリストがいるので解説も学術的で最新の内容も入っているのでただ見て楽しむだけではなくしっかり勉強の場になっているため大学博物館が果たすべき役割と来てもらった人に楽しめるような展示の両立が素晴らしいと思います」
――アンバサダーが設立されたきっかけを教えてください。
津島 「アンバサダーができたのは2021年4月で、今年で5年目になります。当時はコロナ禍だったため、博物館のみならず学生同士のつながりが失われるなかで、主に博物館の職員さんと学芸員さんたちが博物館という場所を通して明大生同士でつながる場所をつくりたいという思いからつくられました。明大生が明大生にP Rすることを目的に結成した団体です。当初は、コロナの影響で明大生とのつながりがなくなってしまった神田学生街を紹介する企画などを行いました」
――皆さんがアンバサダーに入ったきっかけを教えてください。
木下 「アンバサダーは新入生交流会に1年生の時に参加して、先輩方の活動や様子を見ているのですが、私はその場で入りたいですと宣言をしました。前例がなかったので先輩方も最初は戸惑っていたのですが、その後ぜひ来てくださいと言ってもらえました」
上村 「私も1年生の時に新入生交流会に参加しまして、(木下)奈映さんや他の先輩方がすごく優しく接してくださりその場で入りたいなと決心しました。小さい頃から家族で博物館に行くこともあったので、ここに入って博物館をP Rすることはとても楽しそうだなと思って今も続けています」
長屋 「去年の6月、バックヤードツアーの参加後にアンバサダーの存在を知りました。明治大学博物館の魅力を明大生だけでなくていろいろな人たちに広報をしてアピールしていく活動をやっていきたいと思って参加しました」
津島 「私は、高校の先輩がアンバサダーに所属していた関係で大学入学前からその存在は知っていて、博物館に興味がある仲間が出来ればと思っていました。そして、1年生の秋学期が始まる時期に、博物館の職員の方とお話して、アンバサダーになりました」
――具体的にどのような活動をされているのですか。
木下 「活動は簡単に言うと、明治大学博物館の広報活動と外部の博物館の魅力を紹介する活動の2つに分けられます。三昧塚古墳発掘カレー、千代田区マップ、山の上ホテルについての企画などは、いわゆる明治大学博物館の広報活動に当たります。あとは春頃にめいじろうと一緒にキャンパスにて博物館についてのPRも行っています。外部に向けた活動として、一番大々的だったのは、広島大学総合博物館の学生スタッフHUMsの皆さんとの交流などのために、広島を訪れたことです。その内容をまとめて『ミュージアムめぐり広島編』というガイドブックを作成しました。また、都内や関東近郊の博物館をアンバサダーが訪れて、noteというサイト上にて取材記事を書いたりもしています」
津島 「明治大学博物館を明大生に知ってもらいたいという思いと、国内外のいろいろな博物館や美術館に訪れるきっかけにしてほしいという思いで広報活動をしています。1年生が6人、2年生が7人、3年生4人、4年生が7人ということで少数精鋭でやっていて文系・理系や学年も関係なく仲良く活動している団体です」
――アンバサダーの活動で大変なことはありますか?
木下 「私が思うのは、良くも悪くもみんな自由なので、企画を進めるときに人それぞれペースが違うことです。個性を潰さずに一つの方向にまとめていくことが本当に難しいです。実際に今も、それで悩んでいます。あと、最初に記事を書くときもみんな大変だったと思います」
津島 「noteなどにまとめる場合、いろいろな許可取りが必要になります。ただ見学して終わりなら良いのですが、記事として責任を持って、明大博物館を通して発信する以上、事前に取材申請をして、何度もメールのやり取りをしたり、写真を撮るために職員の方に同伴してもらったりと、かなり丁寧な準備が必要です。大学に入るまでこのような作業をやったことがなかったので、そこが大変に感じます。また、企画を考える際、テーマだけは与えられることもあるのですが、0から始まることも多いです。最初のミーティングで方向性を決める作業は結構大変で、自分たちがどう感じるかだけではなく、他の人たちがどう感じるかを想像するところから始まります。自分たちならどのような時に“博物館に行ってみようかな”と思うかを考えて、そこからさらに俯瞰(ふかん)して、より多くの人に届くような企画にする。特に私たちのターゲットは若い世代なので、同世代の人たちが足を運びたくなるような内容を細かいところまで詰めていく。その過程は楽しいけれど、大変でもあります」
長屋 「私は『子どもれきしアカデミー』に参加しましたが、主催者側として全体を把握していたというよりは、先輩の指示に従って決められたことをこなすという立場でした。今年度は私が担当させていただくことになりましたが、実際に企画者としてリーダーになるにあたって、いつまでに動き出すのかという感覚がつかめていませんでした。なので、先輩方に助けられながら、いろいろサポートを受けつつ準備を進めているという状況です。1年生のときから、ただお手伝いするだけでなく、当事者側に立って物事を考えていく姿勢が大事であると感じています」
木下 「私たちが企画を進めるときには、外部からオファーがある場合もあれば、自分たちでゼロから作り上げることもあります。どちらにせよリーダーという立場をまず立てて、その人を中心に、企画に参加したい人を募っていきます。だから、アンバサダーの中で○○担当というように明確に役割分担が決まっているわけではなくて、リーダー以外のメンバーは流動的です。そのため、受動的になると大変になる、ということも起こり得ます」
津島 「個人的に面白いなと思っているのが、この団体にはリーダーや代表といった肩書の人がいないということです。職員の方が全体を見てくださっているものの、アンバサダー長のような役職は存在せず、学生の中に全体を統括するような人はいません。その代わりに、企画ごとにリーダーや担当が決まっていて、それぞれ責任を持って進めるスタイルです。学年を超えて自然と交流が生まれる仕組みにもなっていると思います」
木下 「(なぜアンバサダー長という役職がないのか)実際に私も気になって、職員さんに聞いたことがあるのですが、ガチガチの組織にはしたくないとおっしゃっていました。だから、私が1年生のときに一つの企画でリーダーをやった際には、4年生に『○日までにこれお願いします』って指示を出す場面もありました」
津島 「そういう意味でも、学年の枠を超えて自由に活動できる団体だなと思っています」
――アンバサダーの活動におけるやりがいを教えてください。
津島 「それぞれ感じているやりがいがあると思うのですが、私はこの前、新2年生が中心となり新入生交流会を担当しました。まずざっくりでもいいから目的を決めようということで、いろいろなキャンパスにいる新入生が集まって交流し、新生活での悩みを相談できる場になればいいなと考えていました。その目標をもとに、2年生が中心になってミーティングを重ね、準備をして、無事に終えることができました。アンケートでは『博物館について知ることができた』『行ってみたいと思った』といった声をもらえて、私たちの目指したことがちゃんと伝わったと感じられたのがとてもうれしかったです。やって良かったと心から思える瞬間でした」
長屋 「私は城西大学水田美術館を取材したときの話なのですが、記事を読んだ人が実際に行ってみたくなるように編集することが難しかったです。記事が完成して公開した後に美術館の職員の方とメールでやり取りをさせていただき、感謝のお言葉を頂戴しました。その時は、とてもうれしくてやりがいを感じられました」
上村 「私も博物館めぐりについてです。今まで、博物館は行って終わりという感覚で、どちらかというと“行くこと”自体に重きを置いていたのですが、アンバサダーになってからは、記事を書くために行くというスタンスに変わって、展示を見ながら考えたり、同行者と話し合ったりしながら新しい視点で見るようになりました。博物館はいいなと改めて気づかされることが多く、すごく楽しいです。また、去年のれきしアカデミーでは小学生がなぜか“土器を作るはずが埴輪ができちゃった”みたいなこともあって(笑)。想像もできないようなハプニングや交流があるのも、この活動の魅力だなと感じています」
木下 「私は大きく二つあります。一つは、他の博物館に取材に行ってnoteを書いたことをきっかけに、SNSの相互フォローが始まり、その後も記事を書かせていただいたことです。具体的には、共立女子大学博物館なのですが、最初はなんとなく行った場所だったのに、そこから明治大学博物館とのつながりもできて、今ではXでお互い交流するようになりました。自分がそのつながりに少しでも関われたという実感がすごくやりがいになっています。もう一つは、アンバサダーの活動は成果物が必ず形として残ることです。パンフレットやnote、新聞、テレビの取材など、何かしらの形で成果が見えます。頑張りが返ってくる感じがあって、それが何よりのやりがいだと感じています」
――ありがとうございました。
[聞き手:安田賢司]
後編はこちらから!
関連記事
RELATED ENTRIES