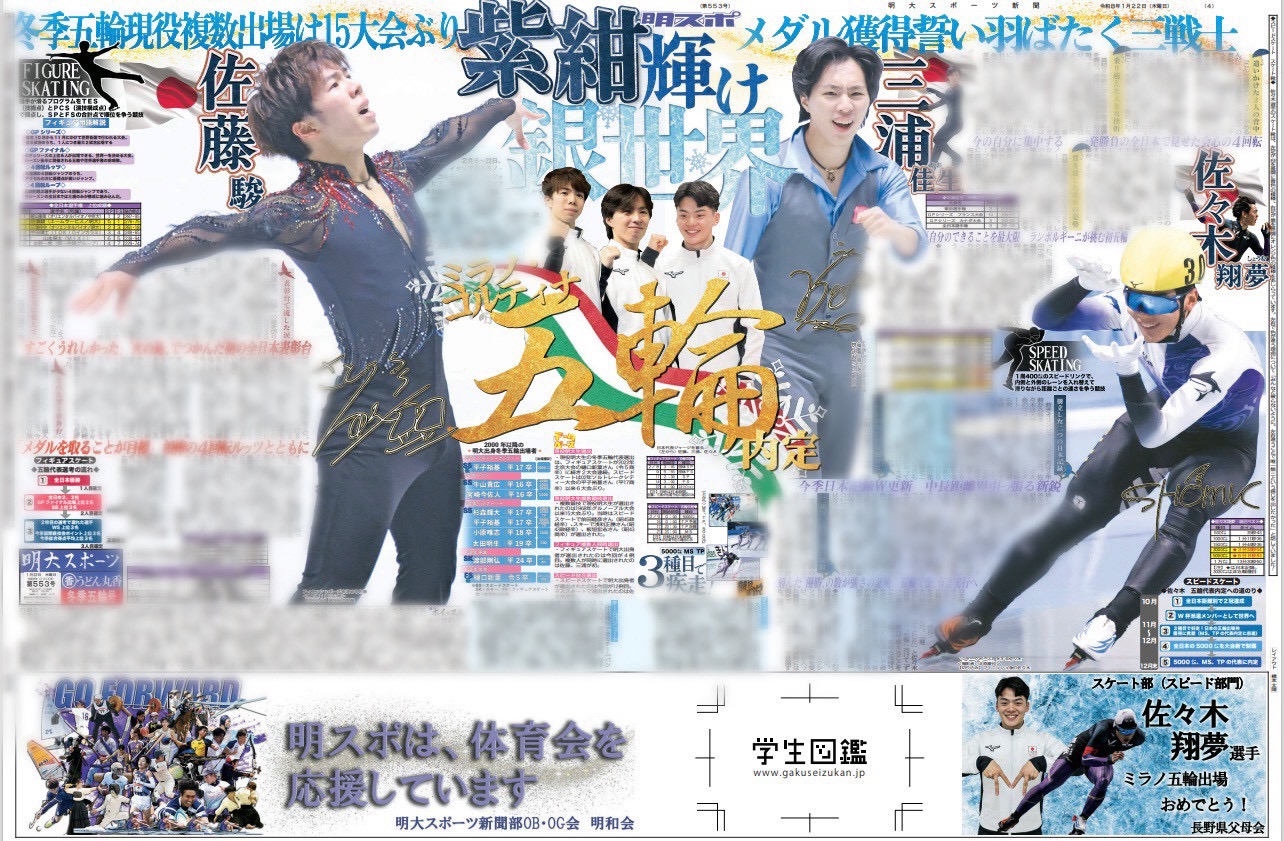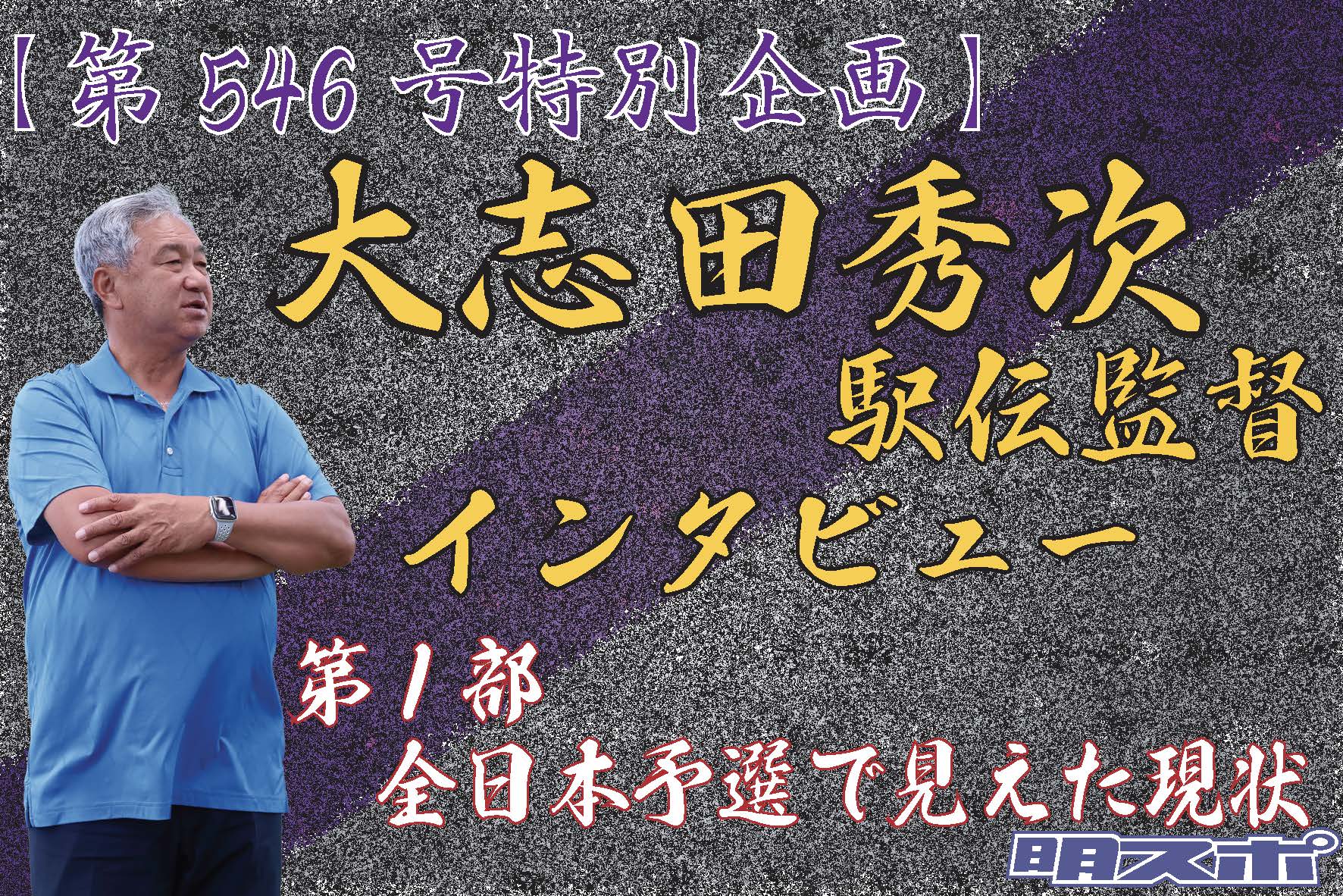
(58)【第546号特別企画】大志田秀次駅伝監督インタビュー前編/全日本予選で見えた現状
明大競走部・長距離部門の新体制が始まって約2カ月半が経過した。7年後を見据えた、大学を挙げての新プロジェクトが開始している中、大きな話題となったのが大志田秀次新駅伝監督の就任だ。東京国際大の駅伝部監督に創部と同時に就任し、わずか5年で箱根路へ導いた大学駅伝界の名将に託されたのは、伝統校・明大の再建。第1回箱根駅伝に出場した「オリジナル4」であるにもかかわらず、近年は「古豪」と呼称される成績に甘んじてきた。そして昨年度は17年ぶりに三大駅伝全ての出場を逃し、紫紺の襷リレーを見ることはなかった。再び「強い明治」と呼ばれるために、新駅伝監督のもと、紫紺の戦士たちはどのような挑戦を進めているのか。今回は明大スポーツ新聞第546号に載せきることができなかった、40分超のインタビュー内容を3本に分けてお届けする。
――まず、全日本大学駅伝予選会の振り返りをお願いします。エントリーの時点で13人エントリーできるところを12人としたり、1年生で1500メートルの河田(珠夏・文1=八千代松陰)選手が入っていたりと足並みがそろい切っていないように感じられました。
「5月の上旬では、13名に絞っていました。4月の下旬には『もし欠員が出ることがあれば、みんな(13名以外)からプラスするよ、入れ替えるよ』という話をしていましたが、その入れ替えメンバーは、次の目標に向かって動いていたので、8人を選ぶ際には13番目の選手も候補に入ることになりました。要するにチーム状況はかなり最悪で、12人でやる必要があったので、13人選んだ中で、1人欠員の12名でエントリーをしました。河田選手に関しては、練習の消化率が決め手になりました。彼はどちらかというと、スピードがあるというより、スピードの持久が長けているので、2分50秒くらいのペースでレースができるのであれば、可能だというところで彼を入れました」
――組配置の意図を教えてください。
「私も大学陸上に携わってから、2年間のブランクがある中での組み立てとなりました。過去のデータ、チームの配置で言うと、1組に関しては、レースの全体を決める重要なポジションと捉え、チームの中でまず安定感のある室田(安寿・情コミ4=宮崎日大)と桶田(悠生・政経1=八千代松陰)を入れました。桶田に関しては、3月の記録会でも29分30秒で走っていますし、練習ではメンバーの中で上位にきていたので、彼をそこに配置することにチームの中で異論はありませんでした。室田に関しては、3組、4組の選手ではまだ経験が足りないので、キャプテンとしてという側面と、序盤を確実に走れる選手として1組に置きました。2組目に関しては、その4つの組の中で、チーム内4番目のグループが配置していたためペースが遅くなる可能性もある中で、確実に走って粘れる選手を置きました。3年生の石堂(壮真・政経3=世羅)に関しては、大学駅伝チームの代表になって初めての試合だったので、非常に緊張していたと思います。力を抜いた状態で実力を発揮できればいいと思って、2組に入れました。3、4組に関しては、チームの要で、これからのチームの主力となる選手、2年生の井上(史琉・政経2=世羅)、成合(洸琉・情コミ2=宮崎日大)と4年生の森下(翔太・政経4=世羅)、堀(颯介・商4=仙台育英)を配置しました」
――当日は気温がそこまで上がらなかったり、雨が降ったり、涼しくなってハイペースになるのではないかという予想がありました。その中でどのような展開を見込まれていましたか。
「まずは選手には確実に走って、ミスをしない走りをしてほしいと思っていました。暑くなるということも想定しながら組分けしたところはありますが、ハイペースになるという部分では、持ちタイムはそんなにいいものではなかったので、後方から様子をうかがって空いたところに間に入って、レースの流れを読み取るよう指示をしました」
――どの組も中盤までは集団についていて、そこからついていくも苦しくなる展開がかなり目立ってしまったと思います。そんな中でも大きな失速はなく、10位にまとめたというイメージがありましたが、全体を振り返っていかがですか。
「7番、6番を狙うには非常にハードルが高いレースでしたが、自分が持っている力を100パーセント発揮できるようなレースの戦術、マネジメントをしっかり考えた上での10位という結果でした。本選出場を逃していますから、結果に満足はしていません。試合が終わった後に選手に言ったのは『記録が速いチームになるのではなく、私たちが目指すのは粘り強いチームである』ということです。また『記録はいいけど、結果予選会は通れません』ということではなくて、記録はなかったとしても『この選手強いよね、明治は強いですね』となっていかなければならないということです。今持っている力ではタイム的にはまだまだ足りませんでしたが、存在感や自分たちのやってきたことを、この2カ月の中で示せたのではないかという話をして『これで終わりじゃない』ということを伝えました」
――監督から見て、この選手はいい走りをした、逆に少し期待を下回ってしまった選手などはいらっしゃいますか。
「全体的に見て、初出場やプレッシャーなど、大学に入って感じたことのない重圧の中で、多くの選手が走り切れていたと思います。中には、自分の走りに対して不甲斐ないと感じ、反省している選手もいました。しかし、そのような思いをチーム全体で共有できたことが何よりも大切だと思います。それは実際に走った選手でなければ分からない気持ちかもしれませんが、そうした姿を見た他のメンバーが何を感じたか、どう受け取ったかという点も、今回の大事な収穫の一つです。走ったメンバーの感想や経験が、チーム全体にとって良い刺激となり、今後の成長につながっていくことを期待しています」
――今回のレースはコンディションが良かったこともあって、どの組も相当なハイペースで進んだと思いますが、近年の大学陸上の高速化はどのように捉えていますか。
「私自身も実業団にいたのでよくわかりますが、実業団にはやはり目を見張るような選手が多くいます。そうした選手たちに今後どう対応していくかが、私たちにとって大きな課題だと思います。ただ繰り返しになりますが、単に走るのが速いだけではなく、強さを持った選手でなければいけないとも考えています。選考会や駅伝といった大舞台で活躍できることが、何よりも求められる資質です。そのためには、もちろん記録も重要です。しかしそれ以上に、果敢に攻める姿勢——守りに入るのではなく、自ら攻めて勝ち取っていく走り方が、これからの選手に求められると感じています」
――昨年度は全日本大学駅伝もそうですが、箱根駅伝の出場権をつかむことができませんでした。競走部が低迷してしまっている要因は、どのように考えていらっしゃいますか。
「私自身の経験から言うと、大学生は高校から上がってきた段階で、高校時代に身につけた基礎的な部分をもう少しブラッシュアップし、それを自分たちの距離やスピードに応じて生かしていくべきだと考えています。そういった観点から見ると、見た目には(しっかりと練習を)やっているように映っていても、実際にはその力の使い方に課題があったのではないかと感じています。良い部分を持っているのに、それをどう生かすかという判断力や意識が足りなかった。また、チームとしてその力をどう強化していくか、どう全体で取り組んでいくかという姿勢も、やや弱かったのかもしれません。もちろん、各指導者は一生懸命やっているので、あくまでこれは私の個人的な印象ではあります。ただ正直にいえば、私が明治に来たとき、積み上げられた土台のようなものがあまりなかったのも事実です。良い環境、そして良い選手がいる中でこそ、自分はどう走っていくべきか、そのために何をしなければならないかを、もっと考える必要があったと思います。その考えが足りなかったからこそ『言うけど行動しない』『わかっているけど実行しない』という状況になってしまった。だからこそ今、そうして言葉にするのなら、それをしっかり行動に移していこうと考えています」
[聞き手:橋場涼斗、春田麻衣]
第2部 〜歩み始めた新生明治〜 はこちらから!
関連記事
RELATED ENTRIES