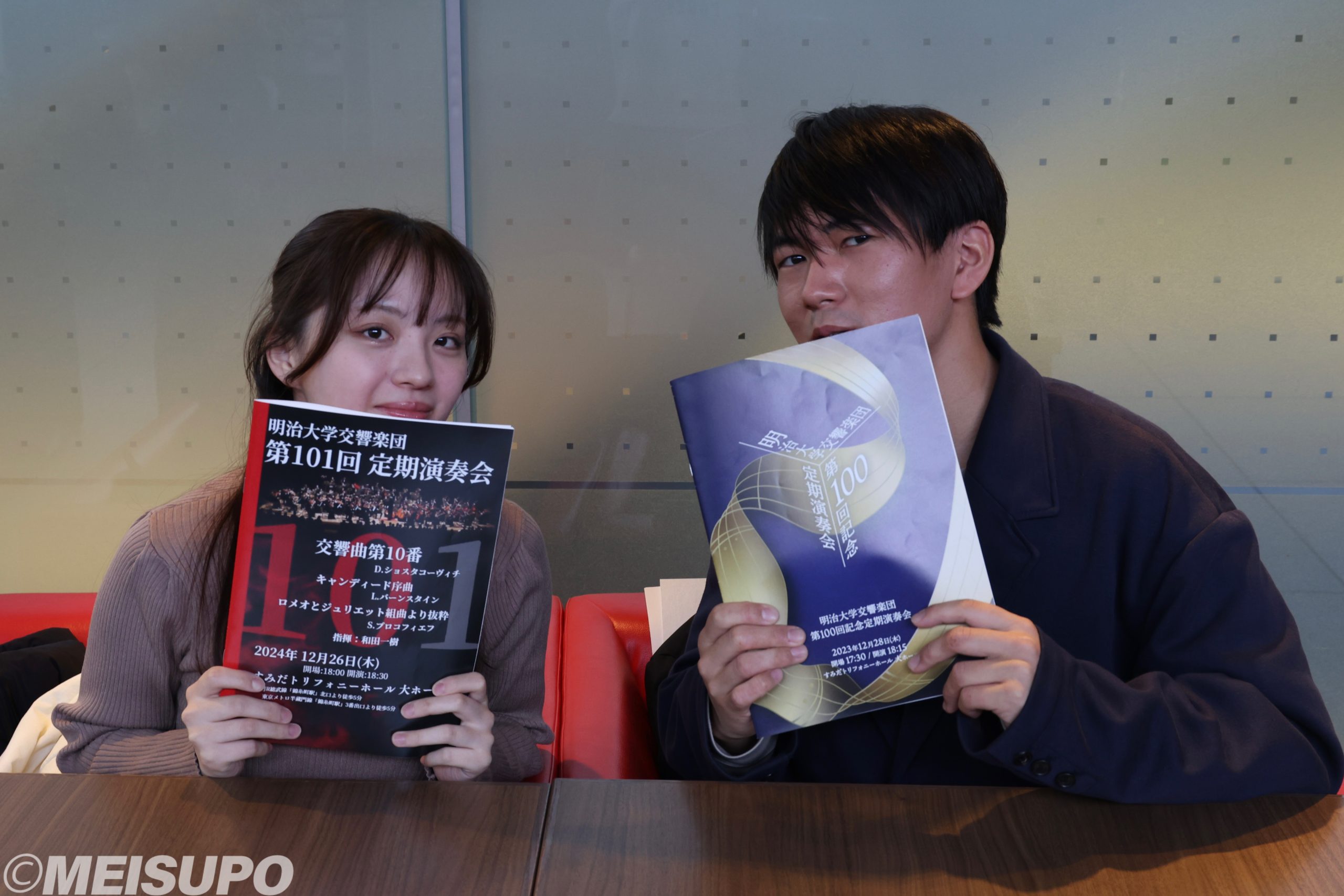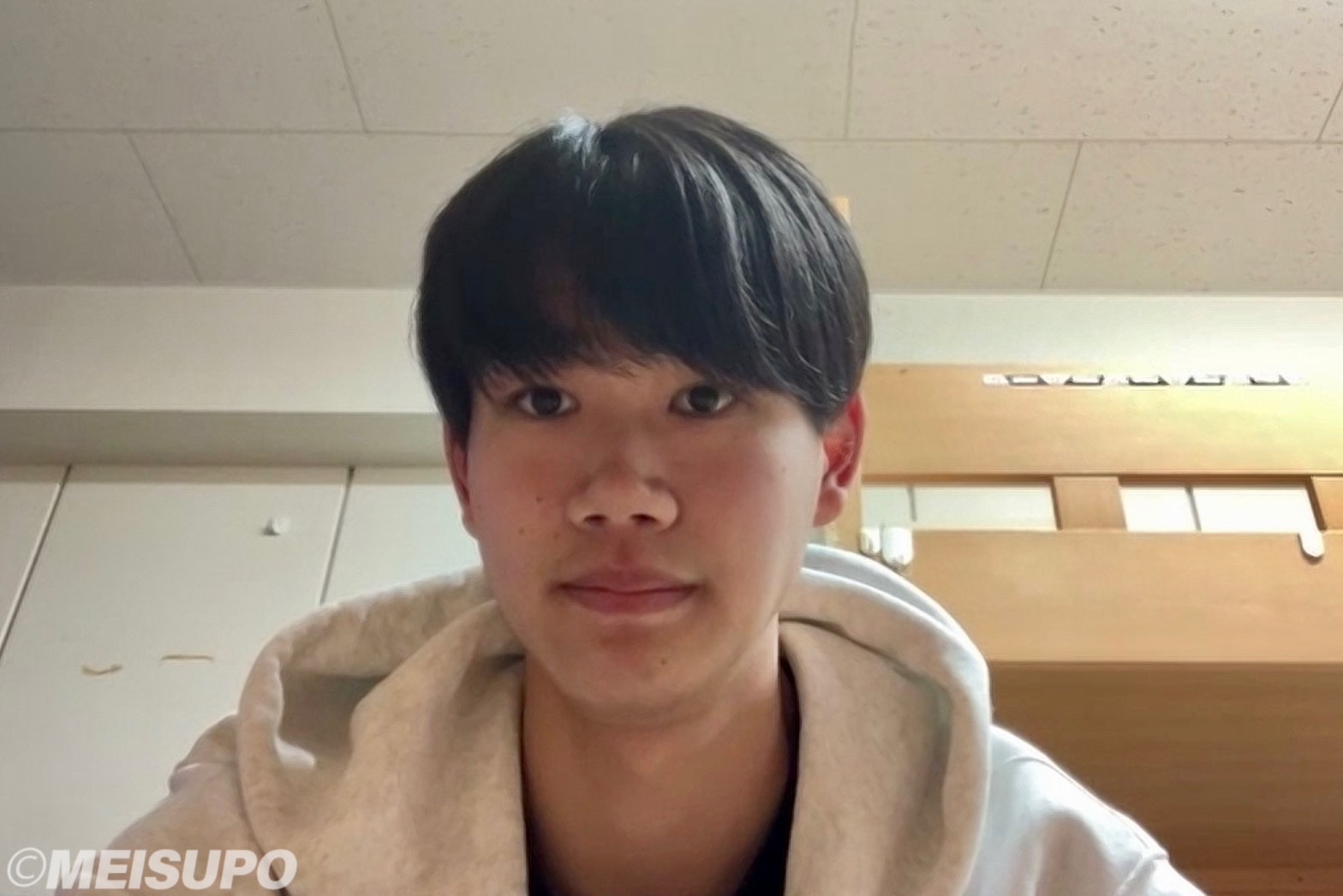(6)特別インタビュー 土屋恵一郎学長 「校歌は〝一人一人が歌うもの〟」
学生にとって〝校歌〟とは何か。現役の学生にとって歌うことが何になるのかは、理解することが難しい。今回のインタビューでは、土屋恵一郎学長に学生一人一人の心の中にある校歌の位置付けについて語っていただいた。
--土屋学長にとって明治大学校歌は身近なものですか。
「学生の時は歌ってなかったんじゃないかな。今もそうですけど昔からやはり神宮とかで歌う機会はあった気がするかな。法学部だったので、なかなか歌わなかったんですが、校歌を歌うことになったのは教員になってからだね。教員になってからは意味を考えながら歌うということを考えてたね」
--好きなフレーズはありますか。
「校歌は一番から三番まであって、二番が明治大学の建学の精神が一番はっきり表れている歌詞があると思う。〝権利自由〟、〝独立自治〟という言葉が出てくるので、そこは印象深かったね。一番よりいい詩だなと思って、駿河台という言葉が自然に歌として出てくることはなかなかないので、いい校歌だと思うね」
--校歌はどんな存在ですか。
「明治大学を象徴する一番大きなものだと思うね。創立以来138年の間にいろんな人たちが明治大学をどういう風に作ろうかと思っていたことが、校歌の中に現れているので、とてもいいことだと」
--学生の校歌離れが進んでいると思いますか。
「学生から離れてみると非常に懐かしく感じるよね。昔だと野球とかラグビーとか学生もいっぱい来ていたし、新宿から提灯行列でこっちまで来るとかね。みんなで一体になってなんかやるチャンスがあったんだけど、そういう時にはもちろん校歌を歌っていました。そういうチャンスに学生がなかなかいないというのは、ちょっと残念かな。せっかく、カレッジスポーツという中で心踊る場面があるのに、そこに来てほしいね。そこに来ればやっぱり明治が勝てば嬉しいし、歌を歌って自分のある記憶の時間ができるじゃん。それを校歌と繋がってると思うんですよね」
--最後に校歌に対する気持ちを語ってください。
「ハーモニーじゃなくて一人一人の個性のままでいいんだ。それで歌として聞こえればいいんだよね。ところがややもすると歌を歌うときに、同じ声を同じ調子で歌ってしまう。違う。ポリフォニックにいろんな声が聞こえてきていいんだ。歌を歌えと強制をするのは、歌いたくない人に強いてしまう。むしろ歌わない人がいてもいい。そういう自由を認め合うのが僕は大学だと思います。でも、歌いたくなってほしい。 一人一人が自分自身の歌を歌おうと思って結果としてみんなが一緒になることの方がいいんじゃないかな」
ーーありがとうございました。
[髙橋昇吾、丸山拓郎、西山はる菜]
関連記事
RELATED ENTRIES