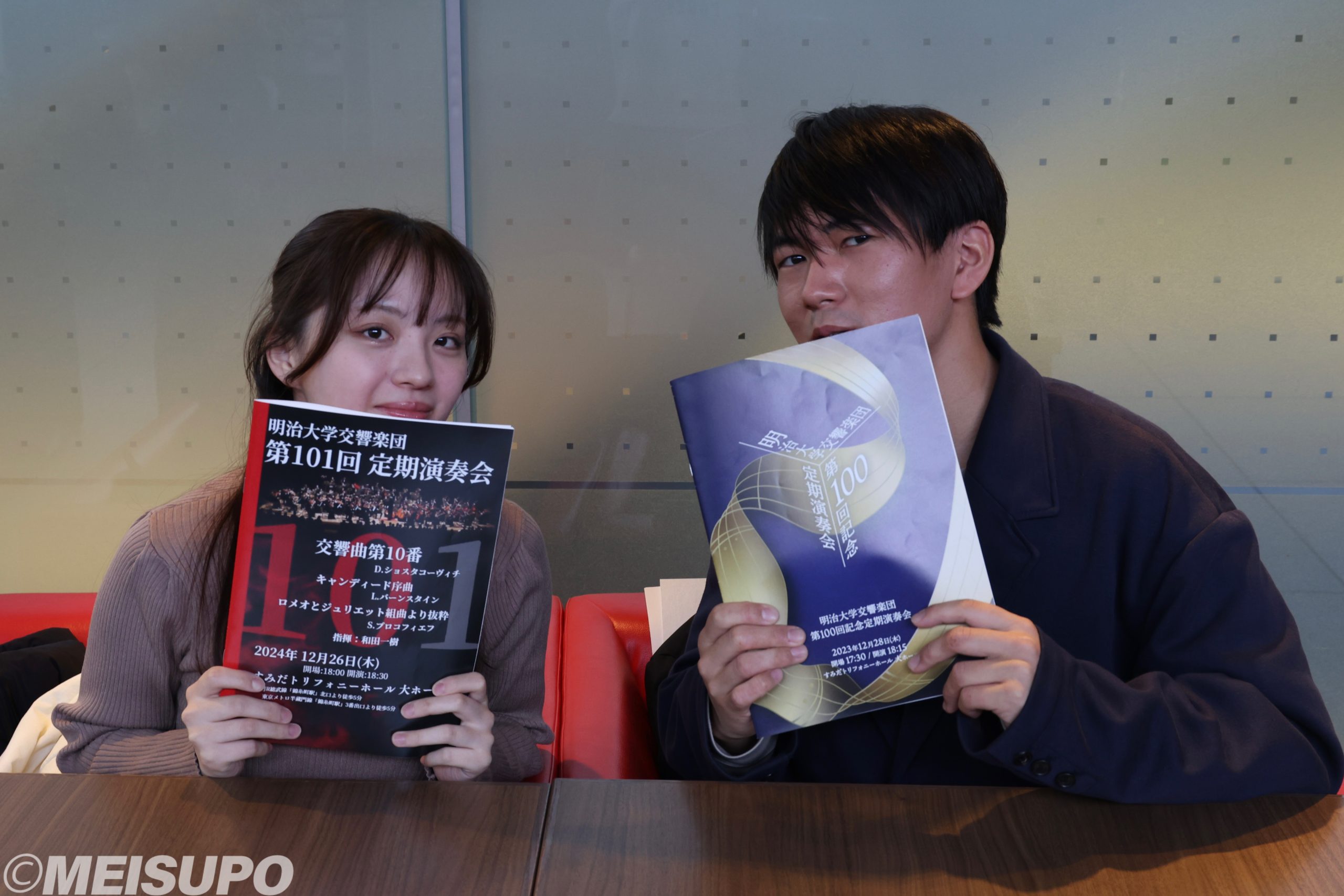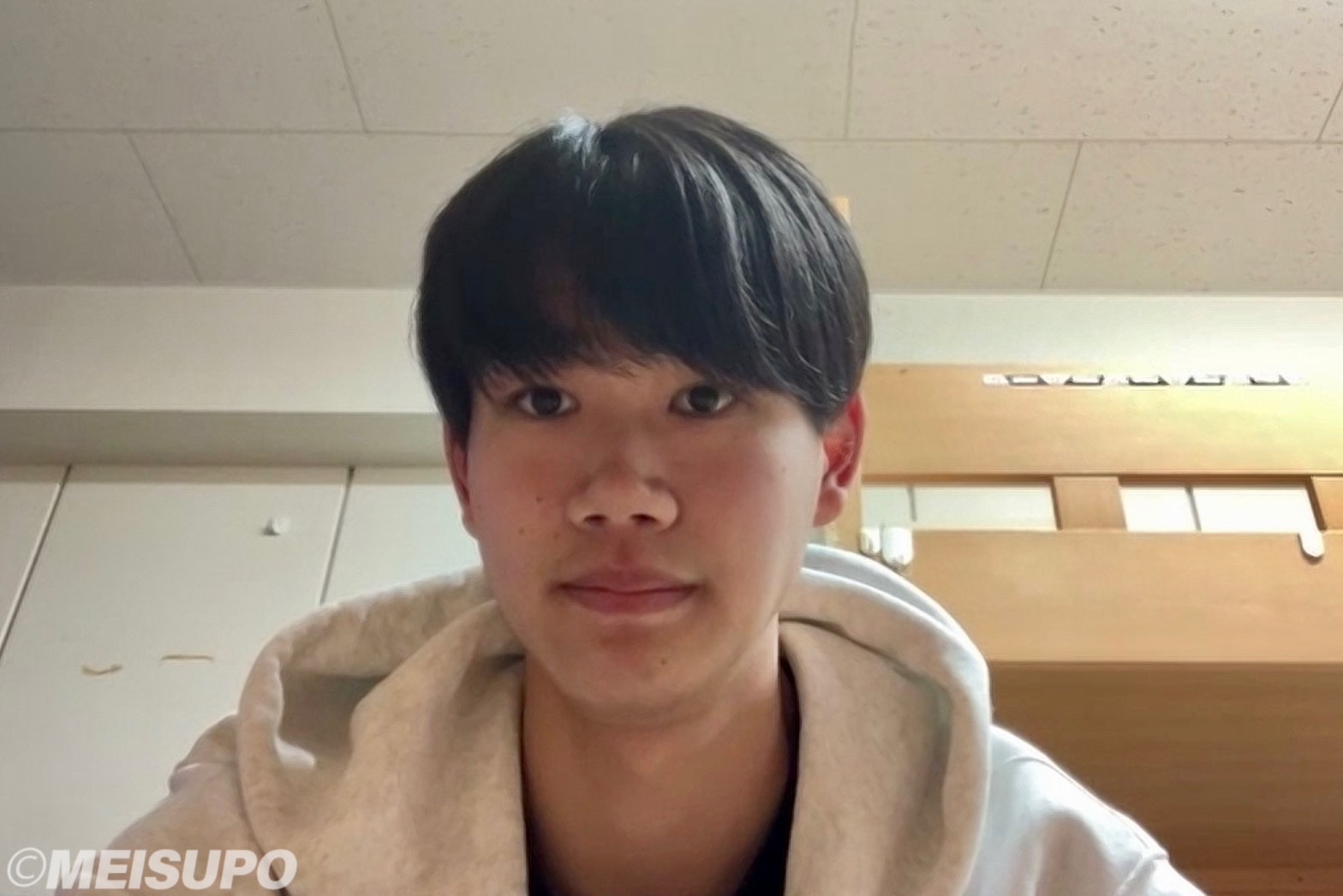揺れ動く就活ルール カギは自己分析
私たちの就職活動(以下、就活)はどうなるのだろうか。9月3日、経団連の中西宏明会長が今後の〝就活ルール〟の在り方について言及し、大きな話題を呼んだ。そんな中、政府は2022年卒業以降の学生についても現行日程を維持させると発表。「まだ何も分からない」といった声が上がるなど、学生の間にも大きな混乱が生じている。大きく揺れる就活戦線を前に、私たちはどうすればいいのだろうか。
売り手市場?
近年の就活市場は、就活生側が有利な売り手市場。19年卒の大卒求人倍率(大卒・大学院卒の求職者に対する求人数の比率)は1・88倍と、7年連続で求人倍率が上昇している。キャリア支援団体『エンカレッジ』明大支部代表の朝原雄也さん(情コミ4)も「企業を選ばず内定を獲得しようと思えば、多く獲得できる」と語る。内定を取ることは以前と比べ、易化したといえる。一方で、就職キャリア支援センターの舟戸一治氏は「(大企業は)以前と変わらない」と指摘。従業員数が5000人以上の企業の大卒求人倍率は、0・37倍。誰もがうらやむ大企業・優良企業からの内定を得ることは依然として簡単ではないのが現実だ。では、私たちが満足のいく就活を行うためには何が必要なのだろうか。それはまず就活の実態、そして自分自身を知ることから始まる。厚生労働省の調査によると、入社3年以内に就職者の約3割に当たる約14万人が退職。その理由として人間関係や、社風が合わなかったなど、企業と自身の思考パターンとの齟齬(そご)が原因として挙げられる。漠然としたままの就活は「企業とのミスマッチが起こる」と舟戸氏。明大スポーツが明大生140人に行った調査でも、自分の価値観や将来の夢が定まっていないと55%以上が回答。大きな問題だといえる。
未来に向けて
そこで有効なのが〝自分を知ること〟だ。自分の価値観、モチベーション、将来の夢を明確にし、さらに夢の実現のために何が足りないかを知る。具体的な行動につなげ、自分を成長させる。そのプロセスの繰り返しで、未来を切り開くのだ。また、自己分析の方法にも工夫が求められる。
一つ目はできるだけ早い段階で行うこと。具体的な行動には一定の時間が伴うのは言うまでもない。さらに「経験の絶対数を増やすことが何より大切」と明大政治経済学部・飯田泰之准教授。飲み会を通じた友人との交流や、休日を利用した旅行など、大学生ならではのさまざまな経験を積むことでより多くの知見を手にすることが可能となる。二つ目は他人の目を通して行うこと。1人では自分の価値観にとらわれ、本当の自分自身は見えてこない。「頼れる人には頼った方がいい」(舟戸氏)。友達や家族、就職キャリア支援センターの職員など、多くの客観的な意見を聞くことで、自分では気付かない一面を知ることが可能に。より説得力のある自己PRができるようになる。 毎年6000人以上の卒業生が社会へ羽ばたく明大。一人一人が自分の将来を見つめ、真剣に己と向き合うことで結果として〝就職力〟の強い大学ランキングで8年連続トップの座を守ってきた。私たちも先輩たちに続かなくてはならない。〝自分を知ること〟。まずはここから始めてみよう。
【渡部伊織】
関連記事
RELATED ENTRIES