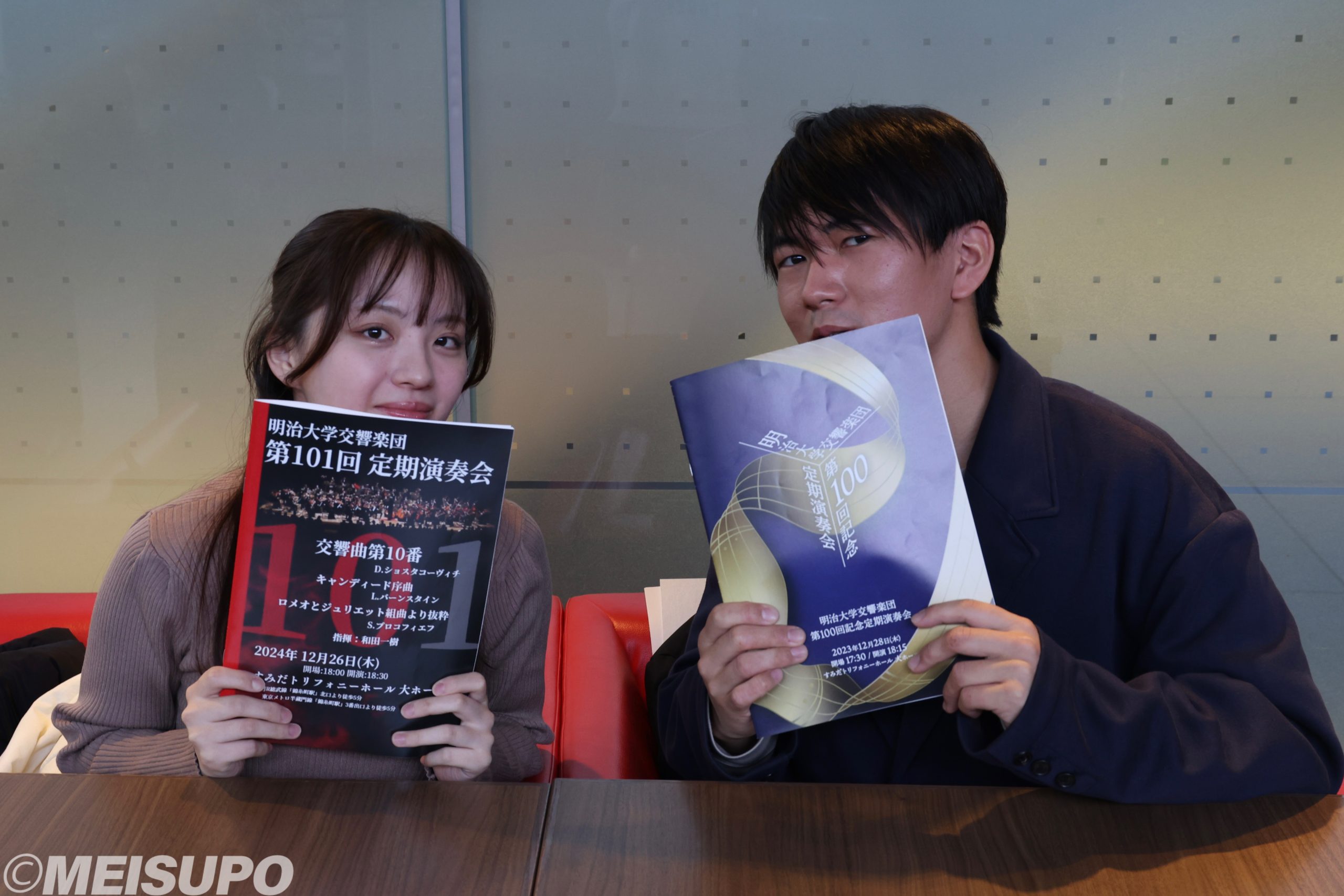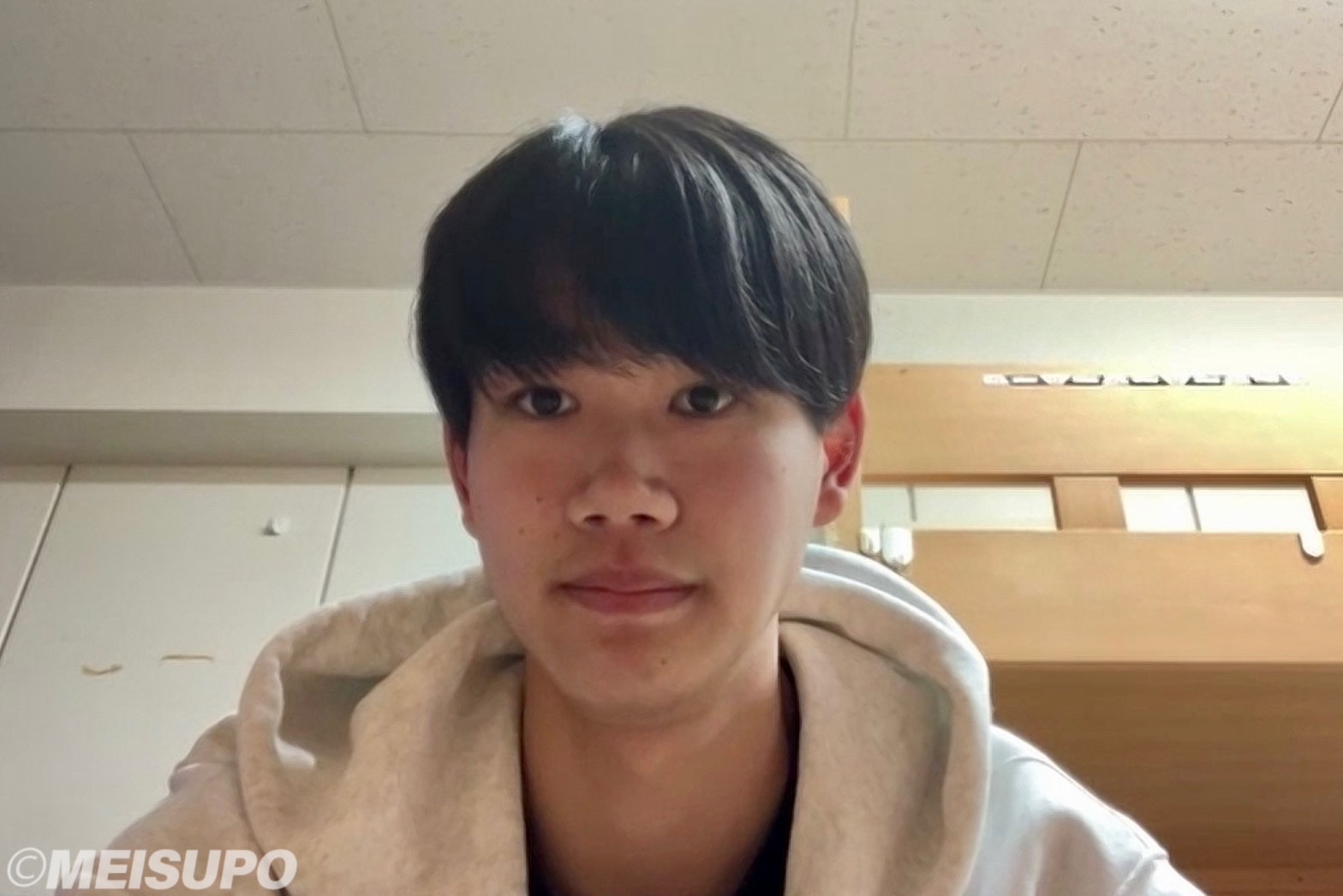吹き飛べ!バンカラ 今こそ明女維新
もう、バンカラなんて言わせない! 今や女性人気で本が出版され、多数の女性有名人を輩出するなど〝オシャレ大学〟として名高い明大。しかし、大学スポーツ界の女性進出はいまだ道半ば。女子学生全体の比率は35・1%(2017年5月時点)まで上昇しているが、マネジャーを含む体育会運動部の女性比率はわずか26・5%(2017年12月時点)と依然として低調だ。来年に設立予定の明大体育会を統括する新たな組織(仮称・スポーツ推進本部)を追い風に、女性への間口を広げたい。
男性組織
男性優位は拭い切れない。明大体育会に女性選手が少ないという現実の根底にあるのは主に二つ。旧体質と体育会の仕組みだ。スポーツ社会学を専門とする政治経済学部の高峰修教授は「なかなか男性の既得権は崩せない。ある意味明大に歴史があることの裏返し」と指摘する。近代スポーツが日本に入ってきたのは明治時代。それとほぼ同時に明大体育会がつくられ始めた。その時代からスポーツの中心は男性であり、いまだ施設面で男性中心の名残がある。女性選手のために既存の活動場を割こうという機運は高まりにくい。
体育会の体制も問題をはらむ。体育会はあくまで課外活動。資金面でも大学からの強化費だけでは足りない。おのずと多くの部の中心である男性、つまりOBからの支援が必須になる。ここでも男性主導となり、使用用途は男子部ばかりに偏る。実際、多くの女性選手は「男性の方が監督やコーチ、施設面で充実している」と不満を漏らす。理解が進まず、女性への裾野が広がらない。
それでも徐々に増加している女性選手。好成績も目立つようになった。だが、男性主導の環境では、セクシュアルハラスメント対策など倫理面での整備も追い付いていない。「男性にマッサージされるのはすごく嫌。でも周りは男性ばかりなので相談できない」と悩む選手もいる。女性への配慮の少なさという点で、管理体制のもろさが露呈している。
変化の時
変革の足音は聞こえ始めている。明大は体育会全体を統治する学長直属の組織〝スポーツ推進本部〟を来年4月に設立する案を構想。スポーツ振興担当の若林幸男副学長は「女性スポーツの振興だけでなく、ドーピング、ハラスメントなどの監視体制もつくり、体育会を統括していきたい」と話す。課外活動と位置付けられていた体育会を大学の管理下にしようと、重い腰を上げた。
この動きは〝日本版NCAA〟開設を見越し、それとの連動を狙ったものだ。スポーツ庁はアメリカ発の組織・全米大学体育協会に倣い、大学スポーツ界全体を統括する機関を来年3月までに設立しようと動いている。現在は競技種目別に連盟が独立しているが、そこに一体性を持たせて管理することが目的だ。〝学業充実〟〝安全安心〟〝マネジメント〟の3原則を軸に、模範的なアスリートの育成を図る。そして試合の観戦などで得た収益を各大学の部に還元することで、より良い環境づくりに生かす。
世界進出
明女、前へ! この二つの動きにより、明大体育会の新体制への準備は整った。女性選手に対応した倫理面、施設などの充実を推し進め、女性選手の母数を増やす。そして、明大から世界へ羽ばたく女性アスリートの輩出をももくろむ。これまで、明大出身の女性五輪メダリストはたった1人。2人目のメダリストが表彰台で笑顔になる日も、そう遠くはないだろう。
【西山はる菜】
関連記事
RELATED ENTRIES