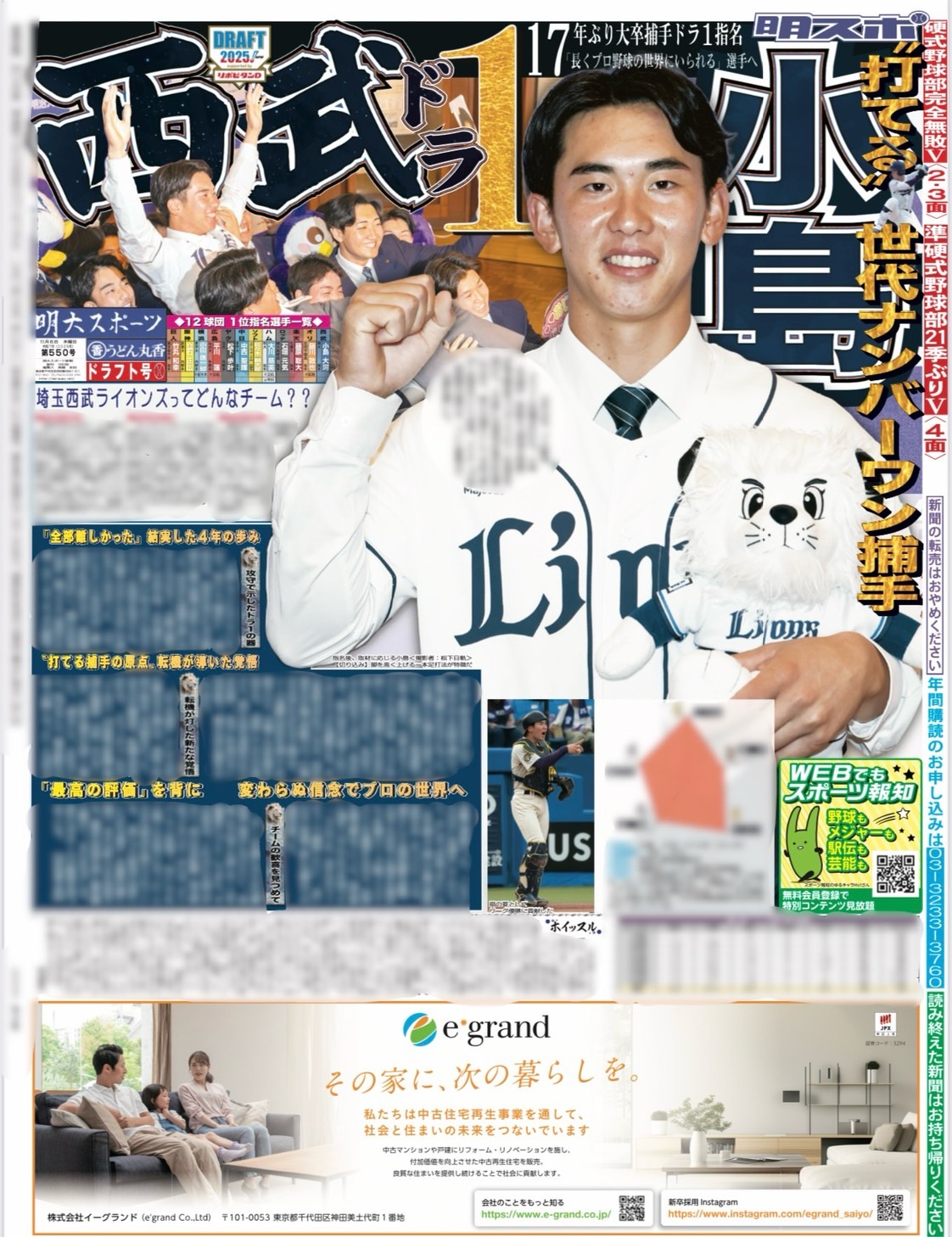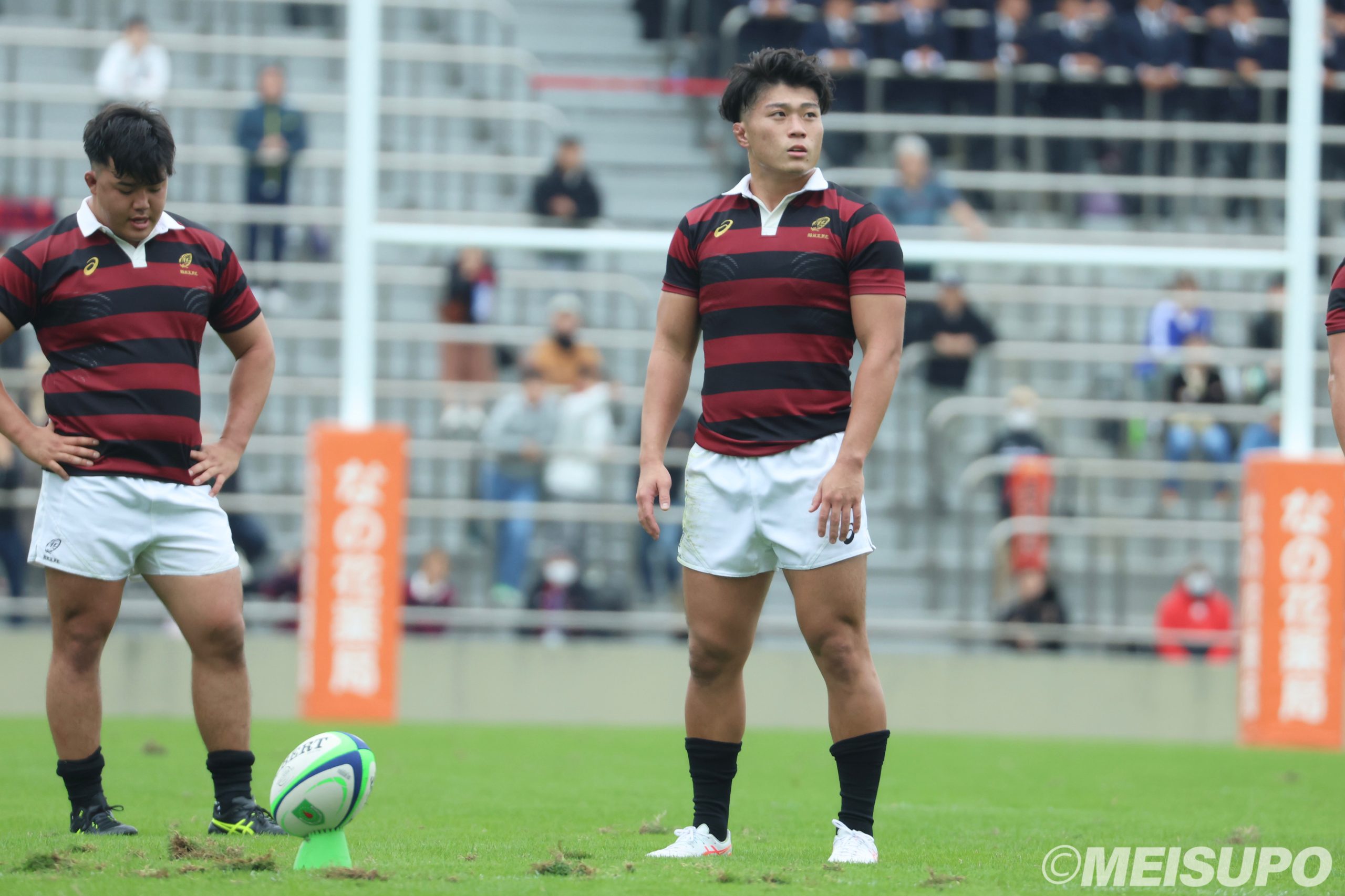野口健が語る大学生活の過ごし方
学生が今やりたいことを見つけるにはどうすればよいのか。登山の清掃活動だけにとどまらず、さまざまな活動を精力的に行っている野口健氏に語っていただいた。
学生はいろんなものを自分の目で見て、自分で感じてほしい。そこからいろんなアクションが生まれてくる。今、僕はいろんな活動をやっているけど、最初から考えてたっていうわけじゃなくて、いろんな現場を見たってことが大きかったんですよね。
自分の言葉でしゃべる人ってのは大体現場を見てるね。本を何冊も読めば、現場に行かなくてもそこそこ文章ってのは成り立つけど、言葉は違うんですよね。いろんな人の話を聞いてるけど、現場に行って自分の感じたことを自分で話す人は説得力があるんだよね。逆に、現場に行かずにいろいろ調べて話す人はどこか伝わってこない。だから、自分で現場に行って、見るのが一番強いよね。見るってことは知るってことだし、知るってことはある意味背負うってことだと思うんですよ。これが、社会人になるとなかなかできなくなるしね。休みも取れないし。学生のうちの特権だと思う。大きなテーマがなくても、現場に行けば勝手に見えてくるものだから。
僕も、最初は清掃活動なんて全く興味がなかったんだよね。エベレストに登山に行った時にたくさんゴミが捨ててあって「汚いな」と思ったら、日本のゴミがあったんですよ。それでいろんな国の登山家から「日本人が汚したんだ」と言われて、悔しくて。それがきっかけになって、だったらきれいにしたのも日本人ならそれで問題ないだろうと思って。そういうふうに、テーマは現地に行けば自然と見つかると思う。 あとは、現場に行かなくても本を読めば物事は分かるんだけど、それって立体的じゃないんだよね。例えば、今やってる遺骨収集でも、どのくらい戦争で戦死してるのかっていうのは調べれば分かるし、知ったつもりになる。だけど、実際にフィリピンに行って洞窟の中で遺体がゴロゴロ転がっているのを見ると、世界が変わる。大体、1個の洞窟で200体ぐらいあって、ほんとにひどいんだよね。そうやって現場で直接見てみると、それまでは平面的だった知識が立体化してくる。生々しいし、リアルに感じる。それが、本当の意味での知るってことなんじゃないかと思う。こういった生々しい現場は、見過ぎると疲れるけど、絶対に見ておいた方がいい。考え方も、人生観も変わる。世の中がそう単純にできているわけじゃないって分かるからね。
きっかけはなんでもいいと思う。例えば、被災地だってテレビで見えてくるものと実際は違う。こういう世間で話題になっている場所を自分の目で確認に行くべきだね。現地には目をギラギラさせて必死に生きている人もいる。それに、最初はボランティアがたくさんいても、これから減っていくでしょう。子供の心のケアだったり、がれきの撤去だったり、おじいさんおばあさんの介護だったり、テーマはいくらでもある。そういう時間の使い方をすれば大学生活はすごく面白くなる。そうやって自分が何をすべきなのか悩むのかが、学生の仕事なんじゃないかと思います。
◆野口健 のぐちけん アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市出身の日本人登山家。植村直己氏の著書「青春を山にかけて」を読み登山を始める。25歳の時に七大陸最高峰を制覇し、当時の最年少記録を更新する。富士山やエベレストの清掃登山活動を経て、現在は太平洋戦争時の遺骨収集活動など、さまざまな活動を行っている
関連記事
RELATED ENTRIES