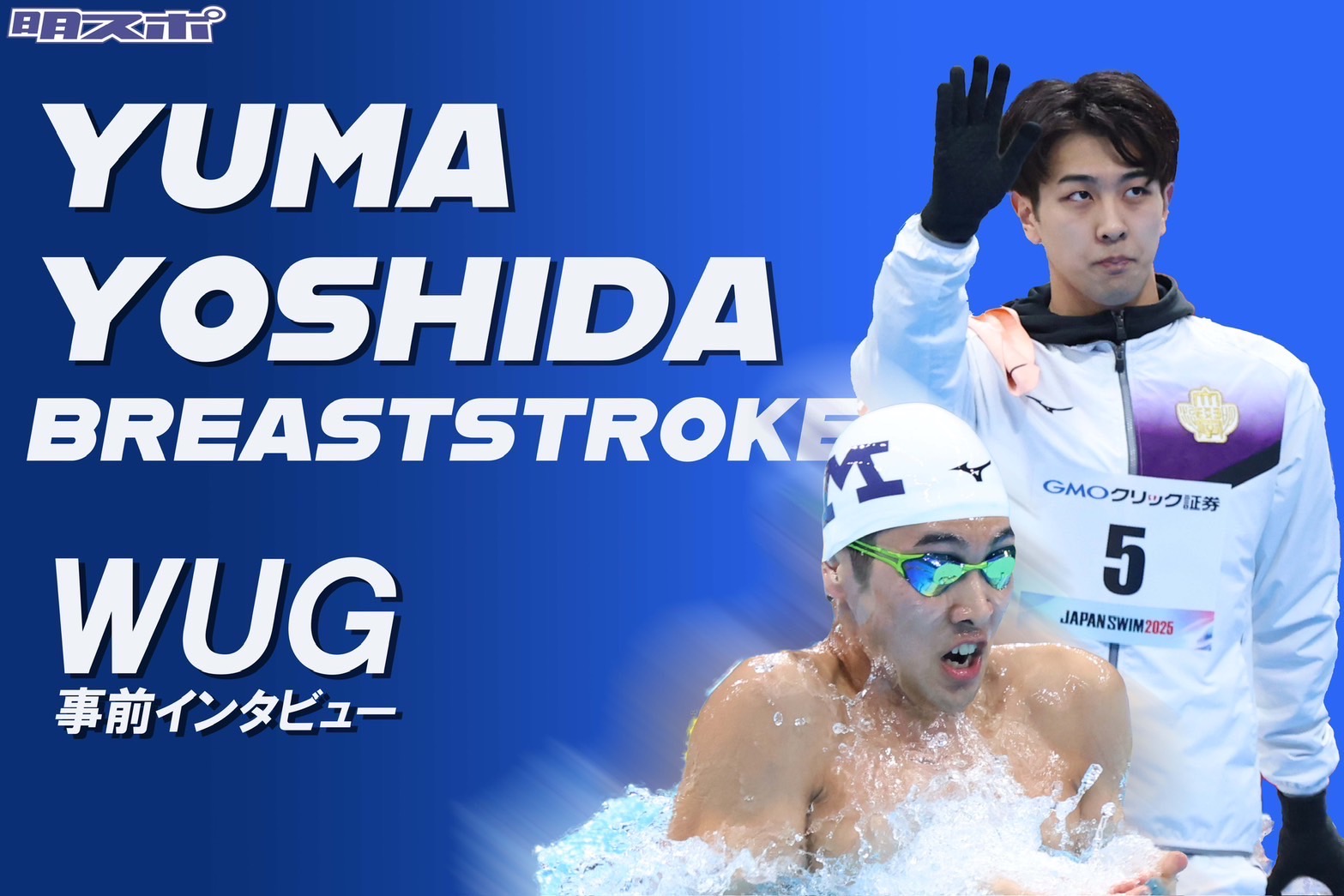(19)マニュアル車に感じた無駄の美徳
わたしは焦っている。普通自動車の免許取得期限が差し迫っているからだ。09年を迎え、さっそうと地元の教習所に乗り込んだものの、ものの1カ月で挫折。マニュアル車を選択した代償――“半クラッチ”が私の前に立ちはだかった。
マニュアル車には、オートマチック車にはない“クラッチペダル”なる第三のペダルがある。半クラッチとは、このペダルを駆使してクラッチ(エンジンの動力を断続する装置)の断続の境目付近を上手く使うことであり、車を動かす上での必須技術だ。クラッチペダルを制するものがマニュアル車を制すると言っても過言ではない。だがその踏み加減いかんで、車は急発進をしたりエンストを起こしたりもする。期待と不安を胸に教習に臨んだわたしを待ち受けていたのは、エンストの嵐。どうしても半クラッチができなかった。繊細な微調整ができなかった。なかなか上達しない自分へのいら立ち、毎度エンストに付き合わせてしまう教習官への後ろめたさ。大学の授業と部活動の多忙も相まって、ある日を境に教習所に通うことをパタッと止めてしまった。
ちょうどマニュアル車に嫌気が差してきたころに、気付いたことが一つ。それは所内に思いのほかマニュアル教習生が多いということだ。マニュアル車が減少傾向にある昨今、「なんで?」と疑問に思った。マニュアルの方がモテるよ!と唆され、選んだわたしは恐らく少数派。なぜ、あえて複雑で面倒くさい操作が要求されるマニュアル車なのか。“大は小を兼ねる”精神はあるだろう。マニュアル車が運転できればオートマチック車も運転できる。その逆は成立しない。だがそれだけではないはず。半クラッチに苦しむ毎日のさなか、その答えを探したが正直分からなかった。分からなかったがこれって粋なことだ。
この世の中は発達し過ぎた節がある。より速く、より簡単で、より快適に。無駄は悪とされ、効率的な物が溢れ返っている。機械への依存度は高く、事を行うのにわたしたちが介入する余地がどんどんなくなって、人間味ある生活が薄らいでいる気さえする。そんな無機的な便利社会への小さな小さな抵抗を見つけた。それがマニュアル車である。もはや生活必需品であるからして、車それ自体が便利社会の代名詞だということはさておきだ。マニュアル車は運転者の指示に忠実であり、オートマチック車がその速度域を機械任せにしているのに対して、自分で速度に応じてギアを変えることができる。もちろん手間がかかる。だがこの手間がいい。時代の流れに逆行し、無駄に挑む姿勢に粋な意地を感じた。
無駄って大事である。いや極論を言ってしまえば、この世の中に無駄なことなんて何一つないのではないか。時間の無駄だとかお金の無駄だとか、人はよく口にして多くを避けようとする。特に最近の人は損得勘定だけで動いていて、合理的人間過ぎる。だが無駄からも学ぶべきことはたくさんある。要は心の持ち様、無駄のとらえようだ。成功者をひもとけば、案外無駄だらけであり、逆に言えばそれを糧にできたからこそ成功者になりえた。成功の裏には無駄があり、無駄こそ美徳なのだ。
教習所に背を向け続けることおよそ5カ月。無駄の重要性に気付きながらも、失効を恐れたわたしはオートマチック車への変更を決断。再び教習所へと通いつめている。無駄の美徳を持てない、いっぱいいっぱいな自分がなんだか恥ずかしい夏である。
第20回は柿澤瑞穂が担当します。
関連記事
RELATED ENTRIES