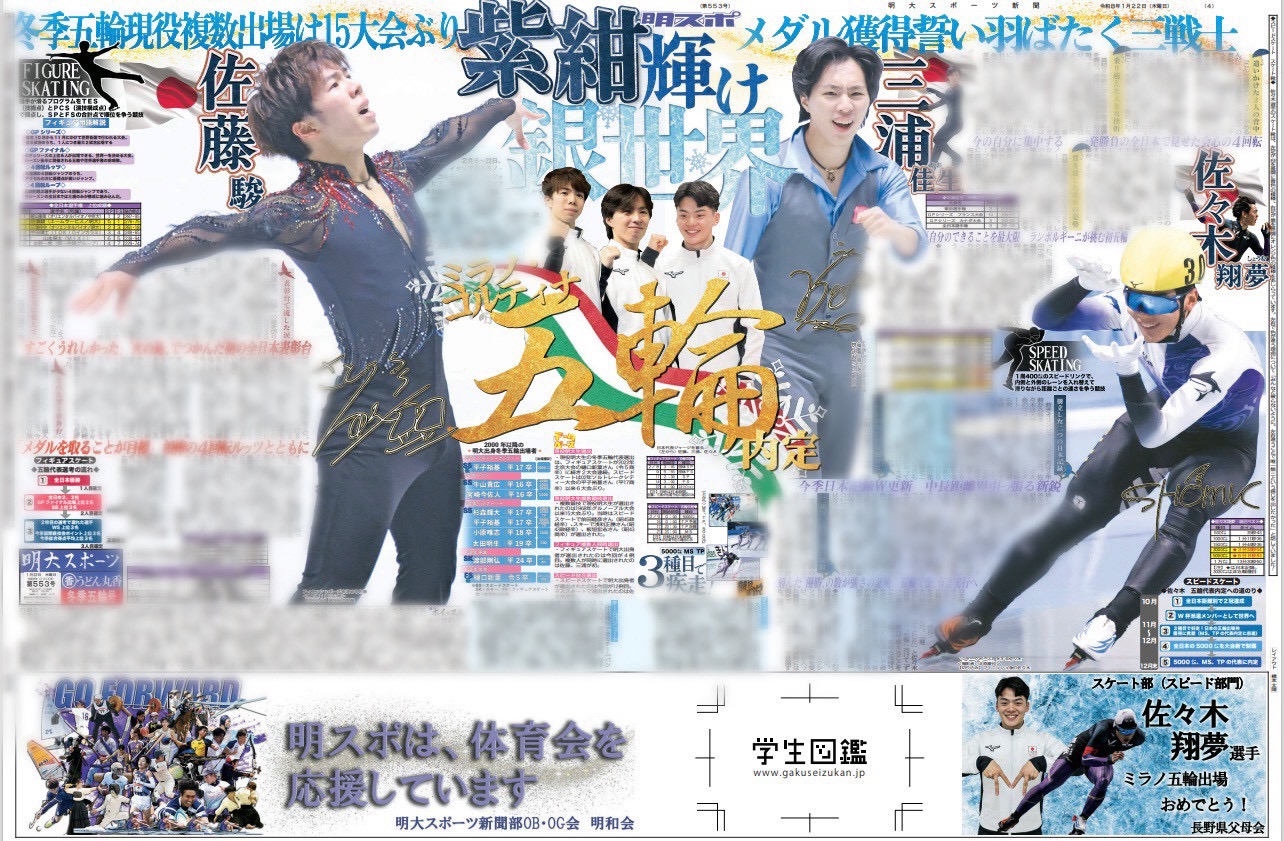常勝軍団・馬術部の1日を追う!
それが終わると、今度は馬の体調検査が始まる。馬の足元に巻かれているものが気になり尋ねたところ、「アイシングです。脚が腫れている馬なんかはこうやって冷やしてあげるんです。野球のピッチャーがアイシングするのと一緒ですね」(立田)だそうだ。1頭1頭馬の足元をチェックし、確認し終わった馬から馬装をしていく。馬装とは人を乗せるために必要な鞍を着け、ハミを掛けたりバンテージを巻いたりしていく作業のこと。馬術を始める前はラグビーをやっていたという江副君(農2)は「毎日やるのは大変です。僕も体験乗馬くらいで止めとけばよかったかな(笑)」と言いながらもなれた手つきで作業を進めていく。馬装が終わった馬から馬場に出され、いよいよ練習が始まる。
この日はまず総合馬から練習が始まり、その後障害馬、馬場馬の順で練習を行った。部員が練習をしているのを見守っていると、柘植主将(法3)に「乗ってみれば?」と誘われ、踏み台をつかって馬に飛び乗る。私自身馬に乗るのは初めてということもあり、「こわっ」というのが率直な感想だった。結構高さがあり、脚だけでバランスをとらなければいけないのだ。「じゃあ歩いてみよう。脚で馬の腹をポンとけってみて」と言われ、言われるがままにやってみると明嶺(5歳)は歩き出した。が、順調に行ったのもそこまで。歩き出した明嶺はそのまま自分の住みかである馬房へまっしぐら。「おい、どこ行くんだよ!(笑)」「止まれ止まれ!」いう部員たちの声が聞こえるが、初めて乗ったので止め方が分からない。「手綱を引いてください」という吉田(賢・政経1)君の指示通りやってみると何とか止まれたが、今度は方向転換ができない。「左に曲がる時は左の手綱を引いて」という動作を実行してみるものの、力加減がまずいらしく明嶺にはうまく伝わらない。結局吉田(賢)君に手綱を引いてもらい、馬場を2、3周したところで私の初乗馬は終わった。
練習を終えたら、今度は練習のパートナーだった馬の手入れを行う。まず、馬装で装着した鞍などを外していく。それが終わると蹄の手入れへ。馬の蹄に装着された蹄鉄(ていてつ)についた泥を丁寧に落としていく。次に体を布できれいに拭く。さっき迷惑を掛けた分も込めて、丁寧に明嶺の体を拭いてあげると、気持ちがいいらしく、欠伸(あくび)をし始めた。最後に「馬の蹄が割れないよう、乾燥を防ぐために塗ります」(立田)という、蹄油が蹄に塗られて作業は終了。馬を場房に戻したところでようやく練習が終わる。
早朝から始まった練習は昼に終わり、食事の時間へ。13時にある飼い付けの担当ではない人は14時半からはじまる夕作業までフリーになる。「毎日どこで寝ようか考えている」(吉田賢)、「30分あれば寝ようかな、みたいな(笑)」(立田)と睡眠不足である馬術部員の大半はここで睡眠を選ぶ。私も飼い付けを終えた後、休憩をしていたのだが、いつの間にか眠ってしまった。
私はまず、餌作りの手伝いをさせてもらった。餌は燕麦(えんばく)、ヘイキューブなどさまざまなものを混ぜて作るのだが、一頭一頭メニューが異なる。馬に合わせた餌を作るためだ。やはり馬は生き物であると再確認した。
次にボロをトラックに積む作業をさせてもらった。狭い敷地をフル活用している明大馬術部のボロ山は、細く、急な坂道を上がったところにある。その道をがたが来ている一輪台車で何回も往復。ようやくトラックの荷台がいっぱいになり、発車すると、届ける担当以外は夕作業が終了。明大馬術部の一日の活動は一段落ついた。一日中部活動を行っていたので「学校がある日は大変そうですね」と私が聞くと、「授業がある日は大変。学校があるから昼の休憩はない、朝起きるのも今日より早い」(佐藤信・商3)と返ってきた。
常勝明大馬術部には最新の道具、設備があり、敷地を効率的に使用しているのかと思いきや、昔ながらの景色があった。失礼ながら、15年間全日本インカレのタイトルを守り続けている王者らしくない風景だと思ってしまった。
試合後の取材で、「普段の生活態度が競技成績に直結する」と長田(おさだ)監督は何度も言った。私はその言葉を聞き、監督は心・技・体の精神を重視しているのだと受け止めていたが、それは少し違っていたかもしれない。馬術部員は馬と共に住んでいる。大切な馬が無事に日々を過ごせるよう、細かいことでも決して手を抜くことは許されない。練習中だけではなく、普段の生活そのものが部活動だ。だらしなく生活するということは部活動で手を抜いていることと同じなのだと思う。今回体験したことで監督の言葉の意味がわかった気がした。
関連記事
RELATED ENTRIES