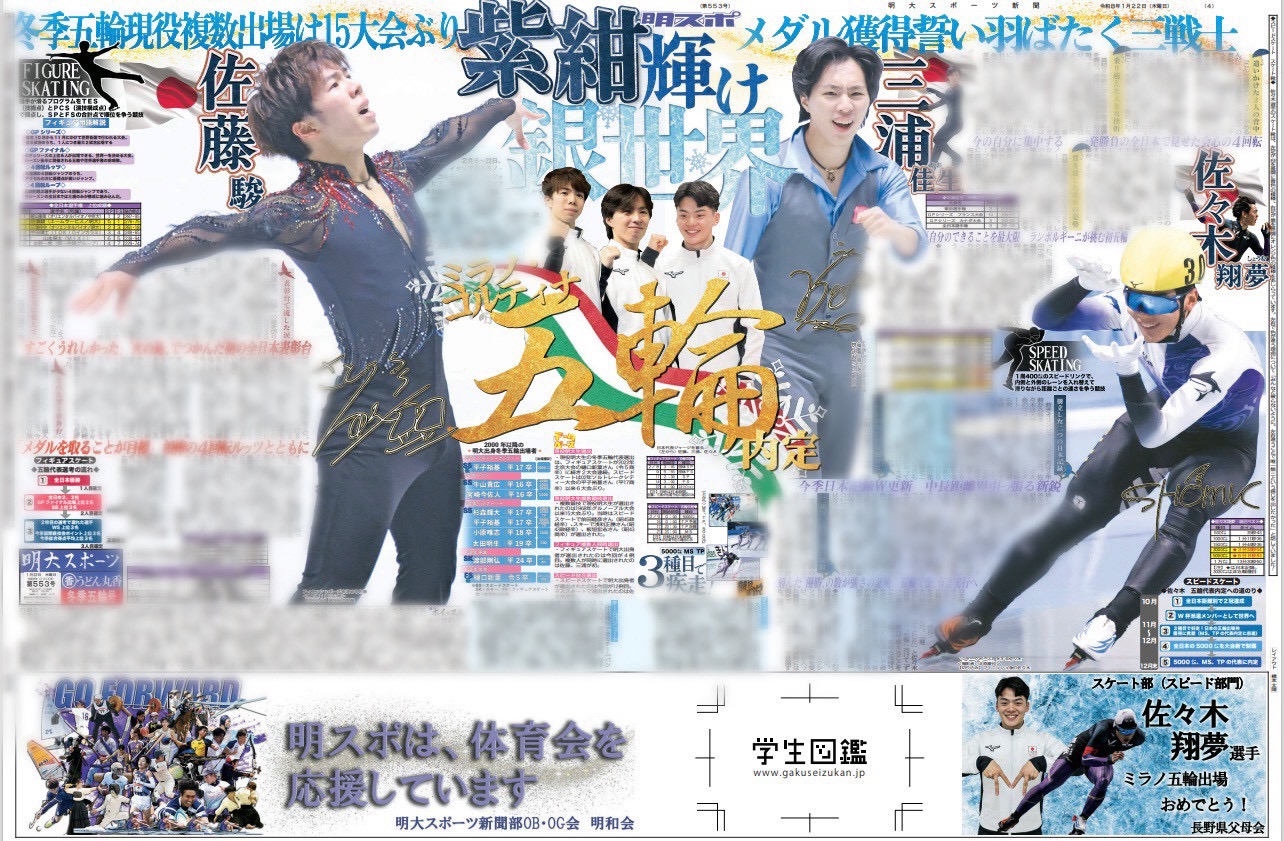(4)厳しい練習から生まれる強靭な肉体
練習前にまず準備運動をするのはレスリングに限らず当然のことだが、ただのストレッチだけでなく、倒立前転や、ヘッドスプリング、後方宙返りなど、マット運動の大技を次々と繰り出す選手たち。マット運動が苦手な本紙記者は、陰でこっそりとできる技だけこなしていった。その大きな体に秘められた身体能力の高さに、いきなり驚かされた。

小田(法4)がタックルの基礎を懇切丁寧
に教えてくれた
準備運動を終えた選手たちは打ち込みを開始。レスリングにおける基本動作とも言える、タックルの練習だ。二人一組となって次々と鋭いタックルを決めていく選手たち。その横で、タックルの「タ」の字もわからない私たちは、まず基本の両足タックルを教えてもらった。選手たちはいつも軽々とやっているように見えるが、実際にやってみるとこれがなかなか難しい。「もっと体勢を低くして!」「もっと体を相手に密着させないと逃げられるよ」。選手の的確な指導のおかげで、しばらく経つと2人共なんとか様になってきた。
しかし、この辺りから体力的に厳しくなってくる。レスリング部の練習では、10分休憩のようなまとまった休みは取らない。打ち込みなどの間の30~40秒のインターバルで水分を補給したりする。こういった効率の良い練習も、本学レスリング部の強さの秘訣(ひけつ)だろうか。体力面で明らかに劣る私たちにとってはつらいことであったが、参加させていただいている以上、甘えずになんとかついていった。大学に入ってから一番根性を出したかもしれない。

押さえ込まれる本紙記者
続いてスパーリングが始まった。選手たちは各自で実戦的なスパーリングを始めるが、持ち技が覚えたての「両足タックル」しかない私たちはスパーリングなどできるはずもない。そこで多賀総監督が相手をしてくれることになった。多賀総監督は現役時代、幻のモスクワ五輪の代表にまでのぼりつめた経歴を持っている。唯一の武器「両足タックル」と、選手の見よう見まねの技で必死に立ち向かったが、終始圧倒され終わってしまった。通常、スパーリングは1R2分単位で行う。2分というと、普段の生活では短いものだが、スパーリングでの2分はとてつもなく長い。2R、3Rと繰り返していくと下半身はもうフラフラ。結局選手たちと同じ数をこなすことはできなかった……。一方で選手たちは真剣な表情で練習に取り組んでいた。少しでも気の抜けたプレーをすると多賀総監督から「もっと前に出ろ!」「そこで止まるな!」と厳しい声が飛んだ。
ようやく練習も終わりが見えてきて、ほっと一息……と思ったところで最後の最後にサーキットと呼ばれる体力練習が待っていた。これはある1人の指示に従って、もも上げや、腕立て、腹筋などを素早く繰り返すというものだ。もう正直体力の限界を感じていたが、人間というものは終わりが見えると力を振り絞れるもの。最後は気力でサーキット3セットを乗り越え、この日の練習が終わった。
久々に感じる肉体の疲労感とともに帰路についたが、レスリング部の真のすごさを認識したのはその翌朝だった。筋肉痛だ――レスリングでは常に低姿勢を保つため、下半身の筋肉は悲鳴をあげた。また上半身も、腕はもちろん腹筋、背筋など全身が筋肉痛に見舞われた。素人ではたった1日でこのような状態になってしまう練習を、毎日のようにこなす選手たち。彼らの強さの基盤はこの強じんな肉体にあるのだろう。重度の筋肉痛に苦しみながら、私はただただ感服するばかりだった。


関連記事
RELATED ENTRIES