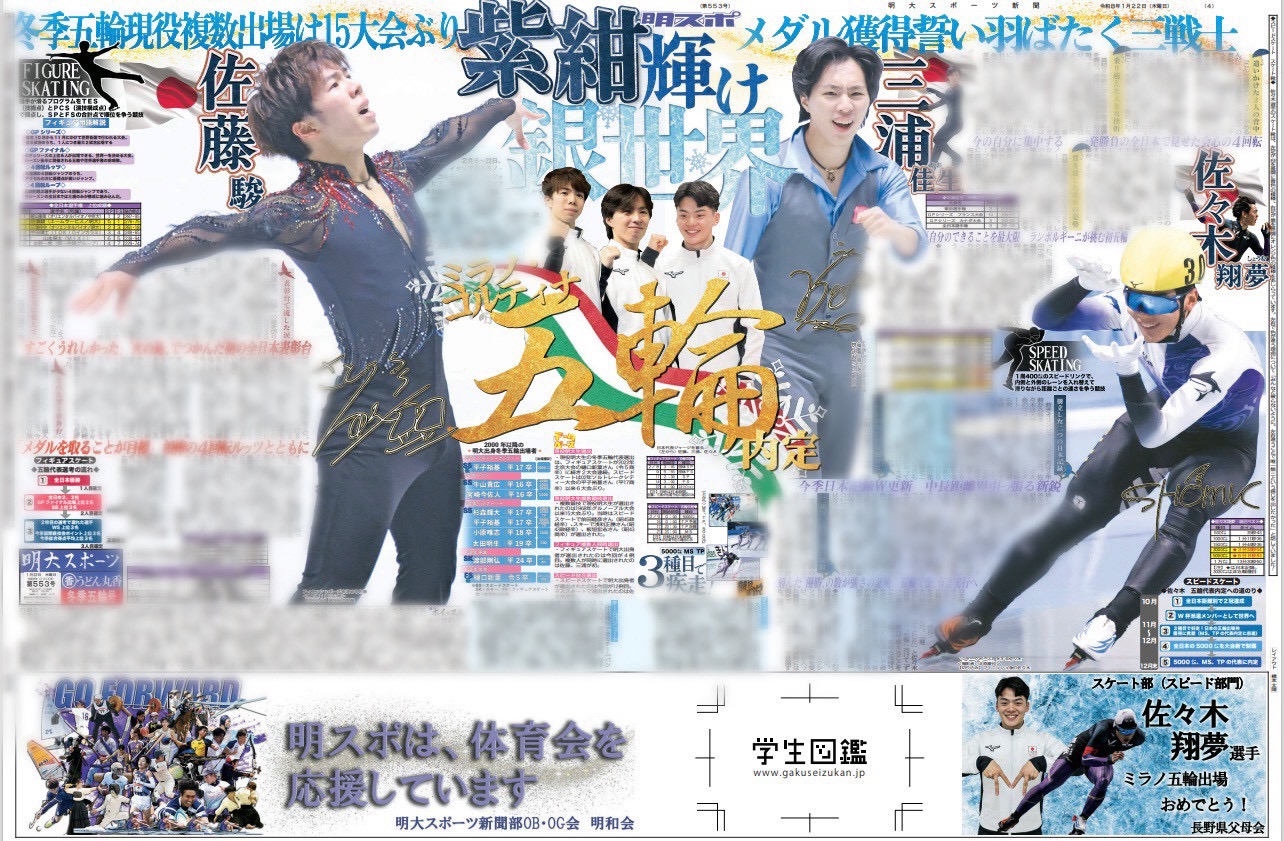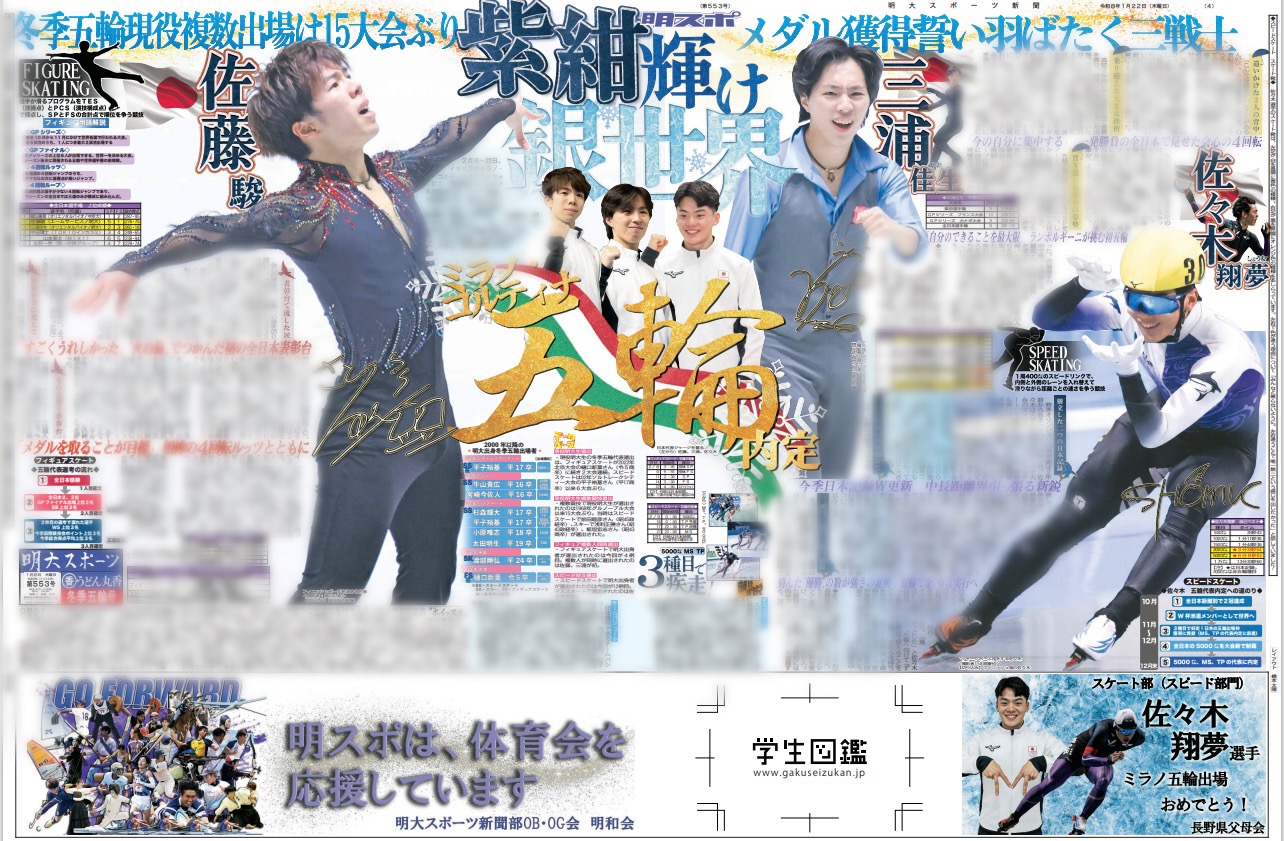明大スポーツ第539号 留学特集対談企画
明大スポーツ第539号3面では、留学についての特集を掲載。本企画では、明大の留学制度を利用して世界各国へ飛び立っている下山田新菜さん(国際4)、垣浦ジェイさん(政経3)、丸山由都さん(政経2)に対談取材を行った。
本記事では、紙面に掲載し切れなかったインタビューをお送りします。(この取材は7月6日に行われたものです)
――それぞれの留学先を志した理由を教えてください
下山田「一番最初は、漠然とした憧れだったと思います。元々私は英語が好きだったというのもありますが、『とにかくアメリカの大学生活がしたい』みたいな漠然とした憧れからだったと思います。でもそれだけでは留学には行けないので、そこで何がしたいのかを考えて、そういう書類も作りましたが、はじめは憧れだったのかなと思います」
丸山「私も英語を勉強することが好きで、海外で自分の力で生活することへの憧れがありました。私の場合はアジアの国を留学先として選ぶことが多いですが、理由としては、アジアが日本と密接に政治や経済の面でもつながっているからです。アジアの国々をもっと知って、日本を別の角度から俯瞰(ふかん)し、世界を知りたいと思ったことがきっかけです。また、留学をして多様なバックグラウンドの人々を知りたいと思いました。幼少期に海外を訪れた時に、コミュニケーションが取れなかった悔しい経験から、英語の勉強をする中で、留学という大きなチャレンジをしたかったんです」
垣浦「僕の場合は、父が日系アメリカ人で。アメリカに行くこともかなり多かったので、アメリカの事情は割と分かっていて。何か一つの物事を捉えるにも、二つの視点だけじゃ絶対に足りないなと思ったので、もう一つ追加しようとなった時に、ヨーロッパ方面かなと考えました。日本の視点とアメリカの視点については分かっていたんですけど、ヨーロッパの視点はほとんど分からなくて。その中で、学部間留学があったスウェーデンを選択肢に挙げました。(これまで経験した留学は)オーストリアで1回です。本当はイギリスに行きたかったんですが、もう募集枠が埋まっていました。オーストリアも雰囲気が良くて、ドイツ語専攻というのもあり勉強していて面白そうでした」
丸山「ジェイさん(垣浦さん)も話していたけれど留学の出願の締め切りは早いので、準備は早めに始めたほうがいいですね」
下山田「交換留学も学部間留学もそうですが、大体1年前から始めるような感じですよね。入学してすぐ、大学のことをよくわかってない状態で調べ出すような感じなので、意外と時間がかかるなと思いました」
丸山「IELTS®︎やTOEFL®︎などの海外大学に出願する際の試験は受けないといけないですよね。この試験のスコア(基準)は、留学先の大学によって異なっているので、どのくらいのレベルがその大学に留学するために必要なのか調べた上で、早いうちから始めるべきだと思いました」
垣浦「2年生から留学へ行くとなると、1年生の春学期くらいから始める必要がありますよね。英語のレベルが足りないというのもあるし、あとは留学先の事前知識というのも足りないので、1年生から志望して2年生で留学というのは本当に大変だと思います」
――いつ頃に留学を決めて、いつから準備しましたか。
丸山「私は、入学前から短期留学をしたいと考えていました。偶然学部からのお知らせで、タイの短期留学があることを知り、1年時の5月ごろに出願と面接をしました。短期プログラムで過ごす日々は濃密ですが、現地を知るには短く感じて、帰国後は英語で授業を受けて生活できる長期留学に挑戦してみたいと強く感じました。その後、1年時の秋学期に英語試験対策をしつつ、どこの国が自分のやりたいことや環境に合っているか選択肢を探りながら考えました。長期留学先の正式な決定は12月でした」
垣浦「僕の場合は2年時の春、夏ごろから志し始めました。1年生の夏でオーストリアに行って『ヨーロッパはいいな』と思ったんですが、(その時は)短期でも英語が話せるなと感じて。でも、しばらく放置していたら全然話せなくなってしまったので、1年間行って、その後もっとコンスタントに英語を話すようにしないといけないなと思いました。やはり長期で一度行って、しっかり話せるようになってから帰ってきたいなと思ったのが大きいですね」
下山田「高校生の時とか、入学前から行きたくてしょうがなかったので、留学のサイトを見て、そこから意識し始めました。国際日本学部にはTOEFL®︎対策をしてくれる授業があるんですが、一人だとどう勉強すればいいのかわからないので。大学1年時の春学期からその授業を取っていて、授業でスコア対策をした感じです。周りも留学に行きたい子が多かったので、一緒にスケジュールなどを把握しながら、大学1年時の春学期は試験対策でした。9月ごろから書類の準備が始まるので、留学計画書という選考の中で一番大事になる書類の準備を始めて、11月に出願するという感じでした」
――垣浦さんと丸山さんは政治経済学部ですが、試験対策はいかがでしたか。
丸山「ACEという政治経済学部独自の授業があります。この授業は少人数で行われていて、試験対策やスピーキング重視の授業など、自分の目標にあった授業を履修できます」
垣浦「下山田さんが話したTOEFL®︎対策の授業もありますが、少ないです。それにかなり遅い時間帯にしかないので、なかなか取るのは難しくて。でもACEでは僕と由都さん(丸山さん)は同じ授業を取っていて、それで留学出願に必要なIELTS®︎の試験を一緒に対策できました」
丸山「ACEの授業は、みんな英語の勉強に熱心な子が集まっていて、かつ留学を考えている子が多いので仲間と切磋琢磨(せっさたくま)できると思います」
――留学先で理想と違ったことや驚いたことを教えてください。
下山田「正直、違うことしかないですね。私はすごく心配性で、渡航前とか、一生懸命に色々なシチュエーションを想像して準備したつもりではあったんですけど、行ってみると想像じゃ収まらないというか。ハプニングの連続だし、準備しきれないなと思いました。だけど、そう思ったときにこういうハプニングがあってこそ、お金と時間を使って遠いところまで行く意味があるのかと感じました。心配して準備するのも大切かもしれないけれど、その場その場で、ハプニングを楽しみながら臨機応変に動くことが、本当に必要だったなと思います。違うことだらけだったけど、違ったからこそ柔軟性が身についた気がします」
垣浦「僕の場合は、まだコロナが流行っていた時期で。入国する時は大丈夫でしたが、帰国する時が大変でした。現地でコロナにかかって、僕一人残されてしまって。支援など完全にない状態で、自分で対処する力を求められる基準が僕の想像を超えていました。どこに電話するのか、どこにメールするのか、どこで薬をもらうのか、そういうことを考えながらやるというのはかなり大変でした」
丸山「私が行ったのはどちらも短期留学で、グループで一緒に行ったので留学前に不安とかはなく、かつ私は楽観的な性格でもあるので『なんとかなるか、やってみよう』という感じで留学に行った部分もありましたが、理想としていたものとは違うかもしれない想定もしておいた方がいいのかなと思いました。現地に行ったら日本と違うことばかりで驚きの連続だけど、現地の人と交流することによって、その国のことをもっと知りたいなと思うようになったし、好きにもなりました」
下山田「自分の居場所が増えるというのは、すごく心強いですね。帰ってきて就活だったり、不安なことだったりが待っているけど、1年他国でなんとか生きられた自分だからと自信にもなるし、辛い時にすがれる思い出なのかもしれないなと思います」
丸山「日本以外にも友達できるのは強みですね」
――短期留学でもその後もお付き合いのあるお友達ができるんですね!
丸山「はい。私はタイの短期留学で出会った現地の方と、今でも仲がいいです。帰国後も電話したりして近況を話していました。最近その子が明治の短期留学プログラムに参加して、日本で再会することができました。楽しい話題から真剣な話題も話すことができる、とても大切な友達の一人です。短期プログラムは、海外に訪れたことのない人や海外での生活を体験したいという人におすすめのプログラムです。基本はグループで明大の学生と授業を一緒に受けられるので、海外への興味を広げる最初のステップになると思います」
垣浦「留学に自分が合っているかというのもその3週間で考えられますね」
丸山「そうですね。その後どうしたいか考えるきっかけにもなります。私と一緒にタイの短期留学に行った友達には、長期留学に挑戦する子が多いです」
下山田「長期留学に行く前、事前に短期留学に行くというのはすごいなと思いました。私は長期留学の準備に手一杯で、準備しながら、大学の授業もこなしながら、課題をこなしながらで精一杯でした。でも、理想的には事前に短期留学をしてみることで語学の勉強にもなるし、行けたらいいのかもしれないですね」
丸山「そういう留学の準備をする面では、情報収集が本当に大切だなと思います。ホームページを頻繁にチェックしたり、事務室や留学に行った先輩に相談をしたりするのがいいと思います」
下山田「私は留学アドバイザーをしています。きっかけは自分が1年生だったころ、情報収集が大事と分かっていてもアクセスしづらいなという気持ちがあったので、もっと後輩がアクセスしやすい環境を作れたらいいなと思いました。実際にやってみると、相談に来てくれる子と来てくれない子で分かれているなと感じました。例えば『なんでもいいからとりあえず聞いてみよう』と動く子もいれば、当時の私みたいに『質問を固めてから行かなきゃいけないんじゃないかな』とか、大人に相談することにハードルの高さを感じている子もいるので。でも、来てくれる側としては、どんな質問でも、どんな状態でも大丈夫なので。質問受ける側は慣れているので、まず相談に行ってみるというのは大事かなと思います」
丸山「留学に行く準備がまだできていないという人でも、明大には国際団体や留学生と交流する機会もあるので、国際交流に興味のある子はそれらを有効活用するのも一つの手段だと思います。私は2年生から政治経済学部の国際委員会のサポーターズという団体に入りました。そこでも新たな出会いに恵まれて充実しています」
垣浦「僕の場合はそもそも英語圏じゃなかったので、現地の言葉、オーストリアだとドイツ語なんですけど、多少の文章は話せるくらいまで勉強しました。現地の言葉を少しでも話せると、現地の人たちの対応がかなり変わってくるので、現地の言葉を学ぶというのは大事かなと思います」
丸山「本当に不思議なんですけど、一言でも現地の言葉を話すと、急に心を開いてくれるのを感じます。そうやって興味を持って歩み寄ろうとする試みが、現地の人からするとうれしいのかなって。もし自分が相手の立場だったら、うれしいですし」
垣浦「日本語で片言でも話しかけてくれたらうれしい、それは本当にありますね」
下山田「歩み寄る姿勢。大事ですね」
――留学してこれを経験したから強くなれたというエピソードはありますか。
下山田「先ほどもハプニングの話をしましたが、自分的にはそれ(臨機応変に動くこと)が強くなった瞬間だと思います。空港での話ですが、日本の航空会社とアメリカの航空会社で対応が本当に違いました。日本だったら意地でも予約をした飛行機に乗せようとしてくれるし、それが普通だと思っていたので、アメリカでカウンターに行った瞬間『もう遅いよ』みたいな感じで乗れなかったことは驚きで、ある意味カルチャーショックでした。でも、なんとか次の便に乗れるとなった時には『何が起こっても、なんか大丈夫なんだな』と思いました。ある意味強さを身につけた気がします」
丸山「ポジティブな思考が大切ですよね。下山田さんも言っていましたが、飛行機は次の便でも乗れますし。常に失敗から学んでいます」
垣浦「沈み込まないで次に跳ねるというか、もっと上へ気分をあげたりが大事ですね。別の対処法とかも絶対にあると思うので」
丸山「私もハプニング思い出した(笑)。タイの短期留学で、現地学生とバンコクの北に位置しているアユタヤという古代の都市に行った時に、現地学生に『昆虫食を食べてみなよ』と言われて。その時はなんでもチャレンジしたいと思って軽い気持ちで食べたら、次の日にお腹を壊してしまって。それを経験したから『私は昆虫を食べられるってことは、それ以外世界中の国でも全部食べられるんじゃないかって!』今までに食べたことのない食感と味でした(笑)」
下山田「それを経験すると、その下のレベルならなんでもできる気持ち、無敵のような気持ちになりますよね」
垣浦「僕もさっき言ってしまったんですけど、コロナにかかったことが本当に一番のハプニングだったと思います。二番目は飛行機の中に携帯忘れたことなんですけど、それが二番目になるぐらいに大変でした」
丸山「大変だった経験は、今につながって自信にもなるし、こんなことがあったからもう次はへっちゃらだなというように感じさせてくれますよね」
下山田「大変な思いをしに留学行くのかもしれないですね。日本だともう大変な思いしなくなってきているのもあって」
丸山「全部不自由なく楽しく生活できますもんね」
垣浦「大変なことを上回るぐらい楽しいことも多いので、それはかなり魅力だと思います」
丸山「現地の学生と交流する時間がとても印象に残っています。ベトナムに行った時は、友達が若者に人気のコーヒーショップに連れて行ってくれて、みんなでビリヤードをしたり、ベトナムで人気スポーツの羽蹴りをやってみたり、観光のガイドには載っていないような、現地の人だからこそ知っているような場所にも連れて行ってくれました。普段の何気ない会話や学校生活の話とかでも日本とは全然違うなと思いましたね。色々なことを話して新しい視点や、行かないと知れないことを知れるというのは貴重だと思います」
垣浦「僕の場合、現地の人たちは夏休みだったので、その現地の学生は全然いなくて。例えばハンガリーとかポーランドとかイタリアとか、イギリスからの学生とか、日本、中国、そして台湾の学生で集まって、みんなでドイツ語を学ぶという感じだったので、現地の学生というよりも近隣の国々の人の話みたいになっちゃいますが、そこだとみんな話せるのは英語なので、色々英語で話していました。それで、価値観が違いますよね。味覚と言いますか、日本のお菓子で日本人がすごく美味しいと感じるものでも微妙と言われることがあったので驚きました。新しい視点というか、衝撃でしたね」
下山田「私は留学生だけじゃなくて、ジャパニーズアメリカンとか、コリアンアメリカンとかベトナムアメリカンとか、元々住んでいる現地の方もすごく多様でした。やはり日本にいると、同じ見かけをして、同じ言葉を話すというのが当たり前だったので、アメリカに行ってみると、それぞれなんだなというのが、目の前で分かりました」
丸山「みんな違う人生を歩んできてバックグラウンドも価値観も異なっているけれど、今は偶然出会って生活しているってすごいですよね」
垣浦「日系人でも全然日本語が喋れない人は多いので。アメリカに住んでると本当にそうですね。僕の叔母とかも日本語が分からないのでずっと英語で会話をしていたので、やはり違うんだなと思いましたね。いくら元は日本人の人たちであっても…というのは本当に思いました」
――留学を通して学んだ一番大きいこと挙げるとしたら何ですか。
下山田「自分の中での普通が変わったというか、多様化したなと感じました。日本にいるとみんな大体似たようなバックグラウンドを持っていて、人と変わったことをするというのが、なんとなくしにくい環境だなと思います。アメリカへ行ってみると色々な普通があって、自分のアイデンティティのこともそうだけど、それぞれがそれぞれの普通を尊重しているというのが、ほんとに素敵だなって、生きやすいなと思いました。私は人からどう見られるかというのを結構気にしてしまう性格なので、アメリカへ行った時も最初は色々と気にしてしまいましたが『自分がしたいことをすればいいんだ』と思えるようになったのは、アメリカで過ごした時間があるからかもしれないですね」
丸山「自分の性格を改めて客観的に考えるようになったり、自分って何者なんだろうと問い直したりする時間にもなりますね」
垣浦「日本にいる人の普通が海外にいる人の普通じゃないというのは、本当に感じますね」
丸山「私は積極的に行動することですね。やりたいなと思ったことをどんどん挑戦してみる大切さを学んだ気がします。例えば最初に友達をつくるとき、他の国の子だと言語も違うし緊張することがありますが、そこを勇気を出して話しかけてみたり、遊びに誘ったり、道に迷っても人に聞いてみるとか、そういう積極的な行動を積み重ねていくことによって、帰国してからも色々なことに挑戦してみようと思うきっかけになりました。人との交流から学ぶことも多かったです」
下山田「人に話しかけるのが簡単になるし、助けを求めることも簡単になるかなと思います」
垣浦「日本の普通とは違うというのもありますし。あと、僕は他人との生活が大変だなというのを寮生活で学びましたね。日本人学生と2人暮らしだったんですけど、それですら結構2人で共同生活ってなると、事前の生活に関するコミュニケーションというのはすごく大事だなと思いました。いかにうまく共同生活をしていくかというのをそこで学びました」
下山田「私も寮生活だったので、すごく気持ちが分かります。やはり他人と住むのは難しいですよね。それまで何の関わりもなくて、急に同じ場所に入れられて、一緒に住んでと言われるわけですし。その上でコミュニケーションは大事ですよね。日本人はつい、遠慮しちゃったりするかもしれないですが、譲れない部分はみんなあるだろうから、ちゃんと主張して受け入れ合ってというのは大事ですよね」
垣浦「言葉にしないと伝わらないと思います。そういう部分は文化が違うとより(大きい)です。『別に言わなくても伝わるだろう』とか、絶対にないと思いますね」
下山田「多分度合いも国によって違うから、察する能力が高い国と日本は言われているみたいですが、アメリカだと基本的に言ったことが全てなので、察してよみたいなのも通じないし、察してくれないことも悪いわけじゃないので、本当に尊重しあって、理解し合ってという感じでした」
丸山「日本人は察することに長けている一方で、アメリカはダイレクトに気持ちをぶつけ合うイメージですね。どちらもいい点があると思います」
垣浦「ヨーロッパでも多分その傾向は強くて、それこそヨーロッパの国によっても全然違うと思いますが、オーストリアはちょっと気を遣ってくれるかなぐらいの感じですかね。そんな日本ほど察しがいいわけじゃないんですけど、ちょうどアメリカと日本の間ぐらいの察しの良さと言う感じでしたね」
――これから留学を考えている方に向けて留学の魅力を教えてください。
丸山「留学の魅力は人との交流です。他の国の人と話して、英語でコミュニケーションを互いに取って、友達だからこそ話せる難しい問題にも一緒に話したりとかできるので自分にとっては人生のターニングポイントになったと思います。私が短期留学に行ったことで長期留学を志したように、将来を考えるきっかけにもなるし、人生において大切な宝物になると思います」
下山田「魅力を一言で伝えるとしたら、自分をよく知れる時間を作れることかなと思いました。留学に行って、これまでの人生で味わったことがないような、一生懸命生きたなみたいな感覚がありました。例えばコミュニケーションがうまくいかなかったとき、自分の語学力の問題なのか、性格的な部分だから仕方ないのか、と考えて自分と向き合うのでその結果、自分をよく知ることができて頑張って生きているなという感覚になりました」
垣浦「物事に対する新しい考え方が身につきます。例えば何かしら政治的な部分でも、海外のニュースを見ると、全然違う伝え方をしていたりします。日本に対しての見方も全然違います。日本にいるだけじゃ知れない日本を知れると思いました。実は自分の国にはこういう国だということを知ることができるのはすごく魅力だなと思います」
丸山「自分がそこにいるので分からないですが、外から見るとまた違いますよね。一つの考えに固執しないで、一度疑えるというか」
下山田「異文化を体験して、自分の文化と違うなと思ったとしても、留学することによって、その文化もその国の一部だという考えになって受け入れようという気持ちになれました」
垣浦「より柔軟に物事を考えられるようになりました」
――ありがとうございました。
関連記事
RELATED ENTRIES