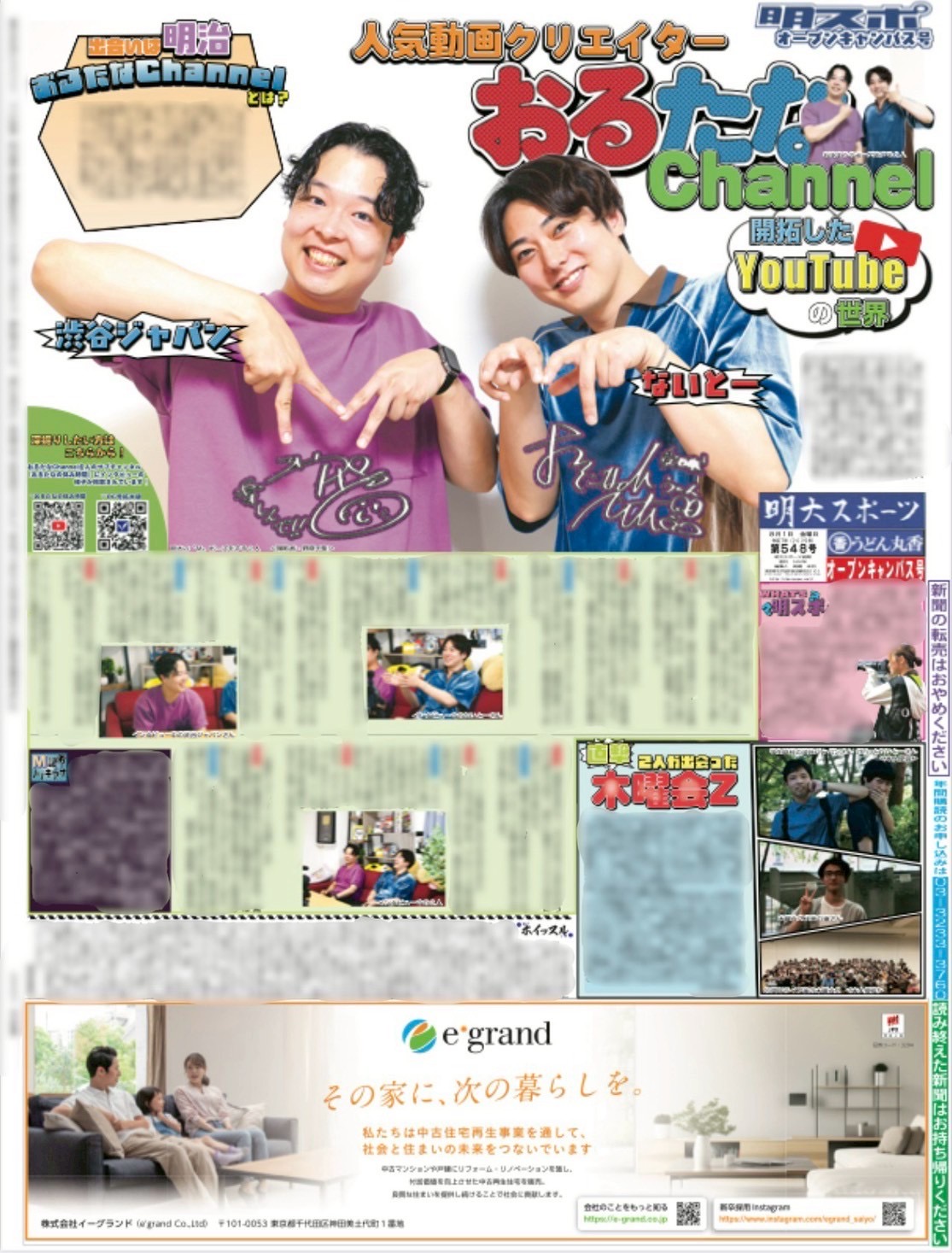(21)明大アイスホッケーあらかると/関東大学秋季リーグ戦
また、五輪種目には男子が1928年の第1回のシャモニー大会、女子が1998年の長野大会から正式競技となった。その後、男子は長野大会からプロ選手の参加が認められ、世界最高のプロリーグ・北米アイスホッケー・リーグ(NHL)からも大勢のプレーヤーが参加している。最近ではNHL・日本人初のプレーヤーとして福藤豊氏(ロサンゼルスキングス所属)が試合出場し、日本をにぎわせた。
明治大学にスケート部が創設されたのは、大正14年。当時は関東地域にリンクも少なく、スケート部のある大学は指を折るほどしか存在しなかった。明大以外に代表的なのが東大、慶大、そして早大である。
明大スケート部(スピード部門・フィギュア部門含む)は、これまで80回の全日本インカレにて総合優勝を49回成し遂げている(その後に日大(10回)、早大(6回)と続く)。さらに3部門完全優勝という偉業は、本学スケート部のみが持つ戦績である(現在3回)。
~主なOB・現役選手~
<日本製紙クレインズ>
・山野由宇
・飯村善則
・鬼頭俊行
・外崎潤
<SEIBUプリンスラビッツ>
・石岡敏
<王子製紙アイスホッケー部>
・曽山雄大
・鈴木雅仁
・菊池恭平
<日光アイスバックス>
・(GM)本間靖之
<その他>
・坂井寿如
日本アイスホッケー連盟強化本部長。GM(ゼネラルマネジャー)として日本代表の強化にあたる。
現役時代はコクド(現・SEIBUプリンスラビッツ)のFWを務め、世界選手権に14回、長野五輪の代表選手として出場した。引退後は、カナダでコーチの修行を経て、現在に至る。
明治では昭和58~61年までプレーしていた。インカレでは4年間で13得点を決める活躍。
~競技説明~
スピードがあり、スティックから放たれるシュートは時速150キロをこえるほど。
体を保護するためにヘルメットやショルダーパッドなどのプロテクターを身に着けた選手が、激しく体をぶつけ(チェック)合いながらパックをうばい合う。
試合の流れは、硬質ゴムでできた「パック」を3ピリオドの間に相手ゴールにスティックで何回叩き込むかで勝負を決めるもの。その迫力から、「氷上の格闘技」と呼ばれています。
~チーム構成~
1チームのメンバーはGK2人を入れた22人で構成します。一度にリンクに立てるのはGKを含め6人です。非常に体力の消耗が激しく、プレーし続けられるのは約1分が限度です。そのため選手の交代は試合が動いていようが止まっていようが、自由に行えます。試合の流れは以下の通り。
~オフサイド~
攻撃側の選手が、パックよりも速く先に相手ゴール側の青いラインを越えた(アタッキングゾーン)場合に発生します。ゲームは中断され、リンク中央付近のスポットでのフェイスオフでゲーム再開です。ただし、パックを保持している場合は(バックで入っても)オフサイドとはなりません。
<オフサイドの種類>
・レッドラインオフサイド
ディフェンディングゾーン内の味方からのパスをセンターライン(赤い線)を越えて受け取ること
・ブルーラインオフサイド
パックより先にアタッキングゾーンに入ること
・パスオフサイド
アタッキングゾーンにいる味方へ、アタッキングゾーン外からパスをすること
~アイシング・ザ・パック~
中央のライン(赤い線)より自陣から出したパックが、誰にも触れない状態のまま、相手のゴールラインを超えると発生します。この時ゲームは中断され、自陣のスポットでのフェイスオフで試合が再開されます。
~その他~
危険なプレーをした選手は直径1メートルほどのペナルティボックスという「反省部屋」に入れられ、時間になるまで試合に参加することができません。その間、チームは一人少ない状況でプレーすることになります。(この状況を「キルプレー」と言い、逆に多い状況を「パワープレー」と言います)
ペナルティー解説へ
<観戦ワンポイントアドバイス>
試合会場(リンク)は想像以上に寒い場所です。ひざ掛けなど防寒具の持参(会場で貸し出しされている場合もあります。)をおすすめします。また、温かい飲み物をひざとひざの間に挟むと足元の冷えが緩和され、より効果的です。
寒さ対策をしっかりして、楽しく観戦しましょう!
<会場案内>
・DyDoドリンコアイスアリーナ
西武新宿線の「東伏見駅」から徒歩0分
・新横浜プリンスホテルスケートセンター
新幹線・JR横浜線・市営地下鉄の「新横浜駅」から徒歩5分
関連記事
RELATED ENTRIES