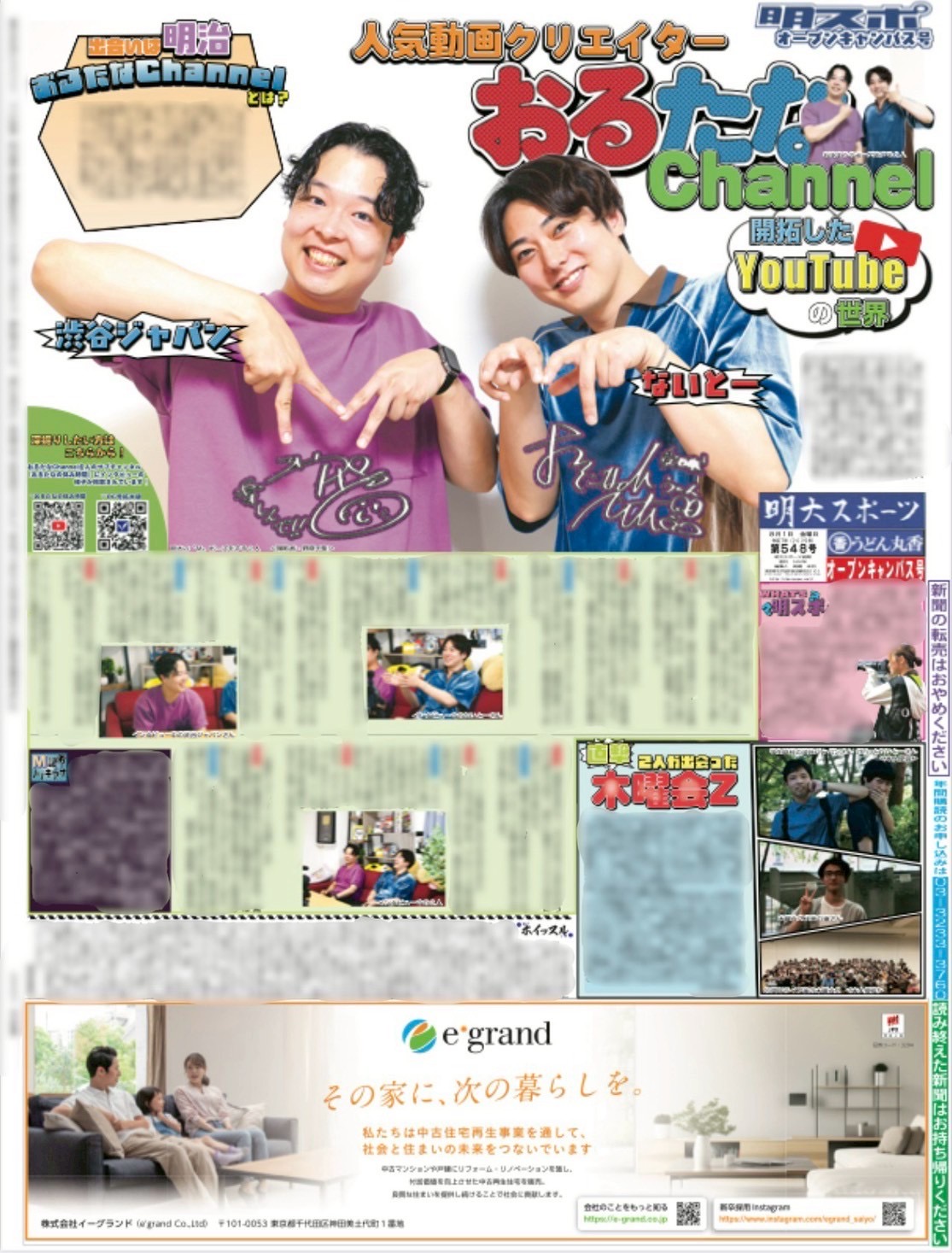(13)‘06関東インカレ特集/関東大学選手権
▼①法大 ②早大 ③明大 ④東洋大
総括「2つの問題と結果」
誰がこの結果を予想しただろうか。今回、優勝を果たしたのは昨年の秋季リーグで4位の成績の法大だった。2位は無期出場停止処分から約3ヶ月で試合出場を果たした早大。そして明治は昨年と同じく3位。昨年の関東インカレ覇者、東洋大は3位決定戦で本学に破れ4位という苦汁を舐めた。
今回の結果にはいくつかの問題が絡んでいた。一つは世界選手権。そしてもうひとつは新ルール基準だ。
<世界選手権>
すでに何回か書いてはいるが、今回はフランスで行われた世界選手権と今回の関東インカレの日程が被ってしまっていた。明治からは菊池アイスホッケー部門主将(政経4)と梁取(政経2)。早大からはポイントゲッターである上野。そして福藤豊の空席に東洋大からルーキーの成澤が招集された。
今回、招集された大学生はみな世界選手権初出場ながらも、梁取、菊池は上位のセットで活躍。早大の上野は早大OBである西脇と組み得点に絡む働きをするなどの活躍を見せた。今大会、日本はイギリスやイスラエルに勝ち3位入賞。4年後のバンクーバーへの希望の光を輝かせた。
<新ルール基準>
さらに今回選手達を戸惑わせたのが、ルールの新たな基準だ。すでにあるルールの基準をもっと明確にしたこの新ルール基準は選手達を戸惑わせた。連盟側がスムーズな試合展開のために導入したものであったが、今大会では審判側もまだ慣れず、あいまいな判定が増えていた。明治に関していえば、それはDFが最も影響を受けたようだ。今まではパック以外のところでの妨害行為やスティックを使っての妨害もある程度は許されていた。しかし、今回の新ルール基準の導入により、パック保持者に対してのいかなる妨害も許されず、パックを持ってカウンターを仕掛ける選手に対して後ろからスティックを伸ばしカットすることもできない。DFはただパスされる際にカットをするか、ゴールの前に立ち、シュートコースを狭くすることしかできない。
<総括>
これら2つの要因は全ての大学に大きく影響した。特に新ルール基準はどこの大学も苦戦しているようで、決勝戦ですら反則数が各校2桁。昨年の秋が平均して6~7だったことを考えればその反則数の増加がわかってもらえるだろう。春の大会はどこの大学もまだチームとしての形がまだしっかりと作れていなかった。そんな中、他大に比べて昨年からメンバーに変化の少ない法大が優勝。今大会では法大の定評のある守備と攻のバランスが格段によかった。
東洋大は攻に偏りすぎ、カウンターを受けた際の対応が遅れ、4位。最強のFW陣を抱える早大も一部の選手の実力は目を見張るものもいるが、チーム全体、特に守備の部分で穴が多く法大に競り負けてしまい準決勝。本学も個々の選手の実力はあるものの、それをチーム全体で生かしきれず、個人プレーになってしまった。そのため連携が上手くいかず、3位止まりとなった。
次は10月から始まる秋季リーグ戦だ。今回の反省を基に、どの大学も新ルール基準の対応をし、秋は万全の状態で挑んでくる。今大会、明治は新入生の活躍は見れたものの、今までの明治の得意とした、素早いパス回しとスピードのある攻めが今大会では生かしきれていなかった。3位決定戦では徐々にチームとして機能し始め、明治らしい試合展開が見られた。だが、明治の実力はこんなものではないはず。秋こそ明治の実力を見せ付けてくれるはずだ!
関連記事
RELATED ENTRIES