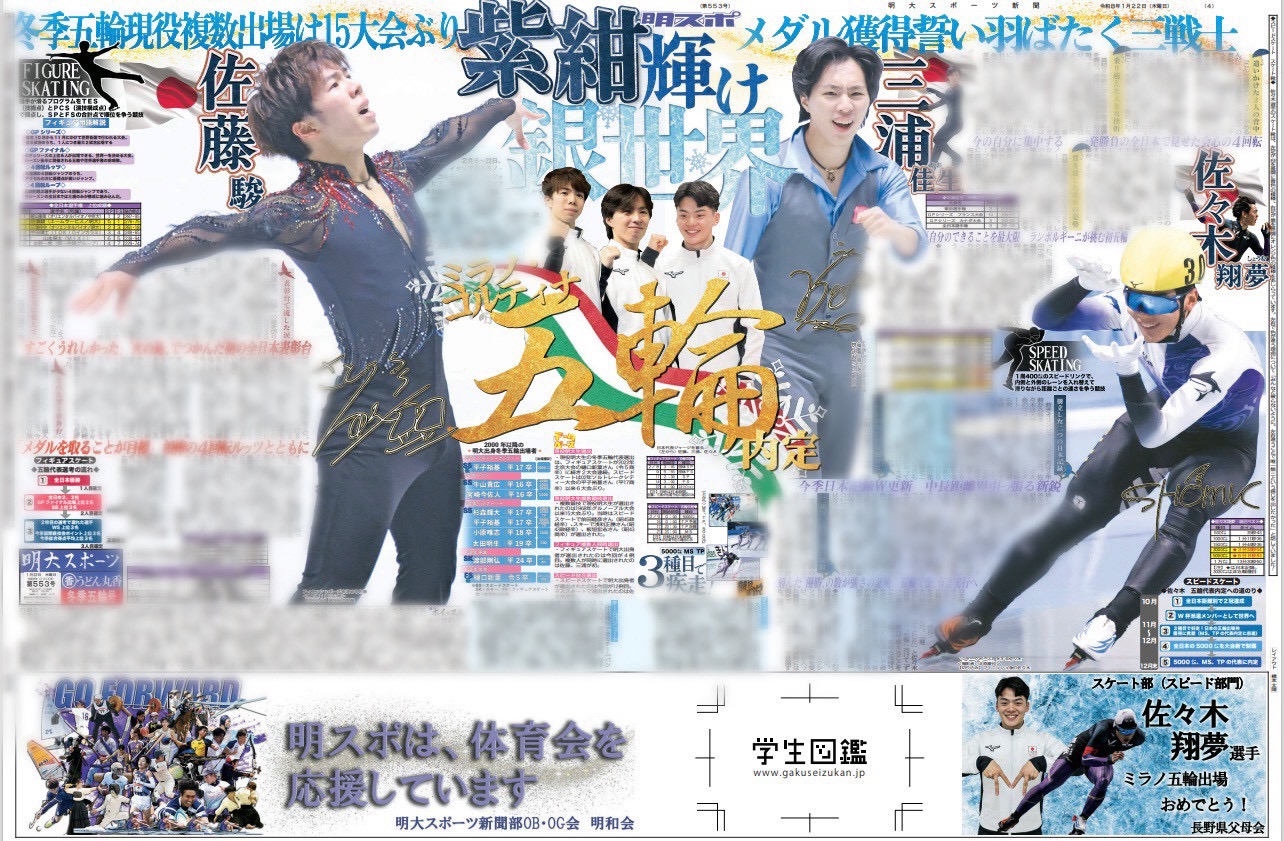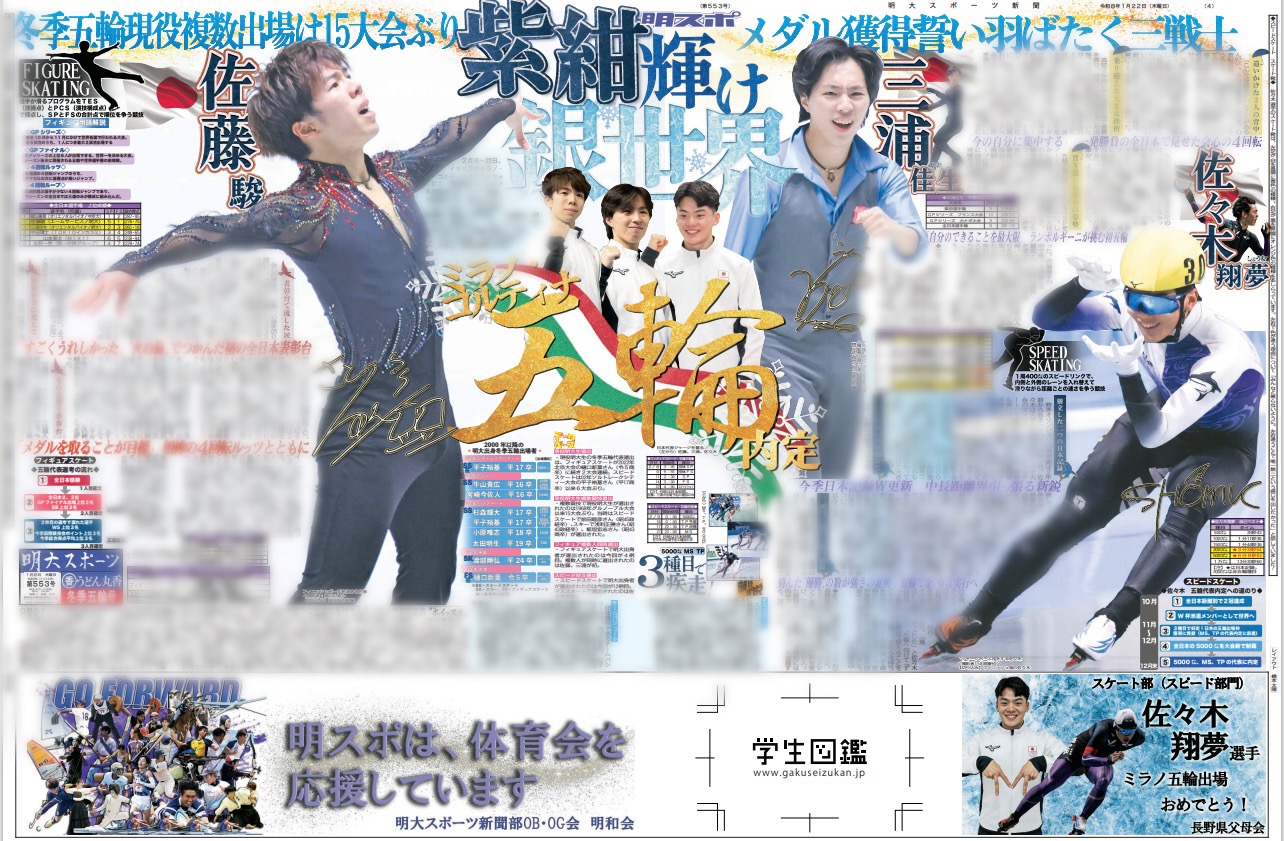八幡山で地域交流プロジェクト開催! 小学生がアーチェリーを体験/アーチェリー部×ローバースカウト部 地域交流プロジェクト
部活動の垣根を越えた、新たな地域交流プロジェクトが始動した。アーチェリー部とローバースカウト部は、明大八幡山グラウンドに地域の小学生を対象とした合同イベントを開催。アーチェリー体験や外国の遊び体験など、それぞれの活動内容を生かした企画を用意した。当日は不安定な天候だったものの午後の部が実施され、参加した子どもたちや保護者、そして両部の部員たちが笑顔で交流を深めた。
◆10・15 アーチェリー部×ローバースカウト部 地域交流プロジェクト(明大八幡山グラウンド アーチェリー場)
▼アーチェリー部
アーチェリー体験教室
▼ローバースカウト部
外国のあそび(モルック、スタッキング、クディッチ)
※当日は雨天の影響で午前の部は中止。午後の部のみ実施。

(写真:手作りの案内表示)
午前中の雨がやみ、雲の切れ間から日の光が差し込み始めた日曜の昼下がり。明大八幡山グラウンドの一角にあるアーチェリー場からは、子どもたちの元気な声が聞こえてくる。今回のイベントに参加した理由を保護者に聞くと「小学校からお便りがきて、子どもが行きたいと言ったので連れてきました」。地域の小学校に配布されたお知らせを見て参加した20人ほどの小学生たちは、両部によるさまざまな体験を楽しんだ。アーチェリー部は、レンタル器具を使用したアーチェリー体験を実施した。的の約3メートル後方から実際の弓を使って矢を放つ。部員が個別に補助しながら、子どもと保護者がこの体験に挑戦した。「弓が重かった」(小学1年生の女子)。中には、実際に持つと見た目よりも重いアーチェリーの弓に苦戦する子も。それでも「子どもたちは思ったより弓を引けていたし、できない子のサポートもしっかりすることができた」(舘柾臣・法3=N)。的に矢が当たったり、高得点を出したりした際には、子どもや部員、保護者が一緒になって喜んでいた。「めっちゃ楽しかった」(小学1年生の女子)。「なかなかアーチェリーに触れられないし、いい経験になりました」(ある保護者)。合間の時間では、部員と子どもたち、保護者が交流する場面が多く見られ、体育会学生と地域のつながりが深まっていた。

(写真中央:子どもにアーチェリーを教える舘)
一方のローバースカウト部は、3種類の外国の遊び体験を実施した。「このような遊びをする機会はなかなかないと思うので、ちょっと変わった遊びをして新しい経験をしてもらいたいなと思った」(南澤明日香・情コミ3=明大中野八王子)。普段から各地で地域交流を行っていることもあり、部員たちはすぐに子どもたちに溶け込んだ。「子どもたちが安全に楽しく活動してもらうことを大切にした」(南澤)。安全に配慮しつつ、子どもたちと一緒になって全力で楽しんだ部員たち。プログラム以外にも震源地ゲームや猛獣狩りに行こうよなど、さまざまな遊びで子どもたちとの距離を縮めていた。

(写真:クディッチをする部員と子どもたち)
アーチェリー部として初の試みとなった今回の地域連携プロジェクト。きっかけは、両部の部員たちによる普段の会話から生まれた。「うちの吉田(麗生・法3=明大中野八王子)が、ローバースカウト部の南澤と仲が良くて、そこの2人で『地域貢献活動を両部でできたらいいね』と話していた」(眞柴大晟・法3=川越)。そこから話は進み、アーチェリー部の地域貢献活動、そして体育会同士の部活動を越えた交流のきっかけづくりを目標に、プロジェクトは進行した。地域交流活動を行っているローバースカウト部の助けを借りながらも、今回の実施主体はアーチェ―リー部。今までそうした経験が全くない部員たちは、当日まで準備に奔走する。「保護者などの連絡の管理を主にやっていたが、一つのメールアドレスだけでやり取りしていたので、返し切れなかったり見落としていたりなど、やり取りが大変だな、と思う部分があった」(吉田)。他にも「何より大変だったのは、この直前期。すごくバタバタで、雨の予報だったり、あとは直前に何が足りていないかを考えたりが大変だった」(眞柴)。そうした前例のない準備活動の末、本イベントは無事開催された。当日は体育会学生と地域の交流だけでなく、イベント後には両部によるそれぞれの企画の体験も行われた。その日のアーチェリー場では、子どもたちや保護者、そして両部の部員たちの笑顔が絶えることはなかった。

(参加した子どもに表彰状を渡す吉田(右)とメダルを渡す眞柴)
「来年度以降も続けていけたらなと思っている」(吉田)。「他の体育会の方とも一緒に合同で活動できたら、もっとより良い活動になる」(南澤)。本イベントの立役者となった両部の2人からは、こうした力強いメッセージを聞くことができた。来年度以降も、この八幡山の地域交流が続くことを期待したい。大学スポーツの主体である体育会の認知度向上のためにも、このような合同プロジェクトを通じた部同士の交流や外部との交流、発信を強めていくことが求められる。弊部でも、以前は一部の体育会とボッチャ交流会を開催した過去もある。今後、このような体育会同士の交流は増えていくのか。私たちも自分ごととして捉えつつ、これからもさまざまな〝明治の今〟を発信していく。

(写真:イベントの合間、空にかかっていた虹)
[渡辺悠志郎]
関連記事
RELATED ENTRIES