
昇段審査 眞下が二段に合格/昇段審査
12月11日、眞下廣誠(政経4=城北)の二段審査が行われた。厳かな空気の中、師範の目の前で稽古の成果を発揮し、見事に昇段を果たした。 合気道の審査では、指定された技を師範の前で披…

集大成 武道館で堂々の演武/全国学生演武大会
全国各地の合気道部員が日本武道館に集結した全国学生演武大会。一心不乱に稽古に取り組んできた明大の4人は、今年度最後の大舞台で堂々たる演武を披露した。 ◆11・25 第6…

昇段審査 安藤が一級に合格/合気道部昇段審査
7月12日、合気道部の前期練習最終日に一級審査が行われた。他の部員が見守る中、師範の目の前で演武を披露。見事に合格をつかみ取り一級昇段を果たした。 今回一級審査を受け…

4年ぶりの有観客開催 聖地で稽古の成果を披露/全日本演武大会
4年ぶりの有観客開催となる全日本合気道演武大会が日本武道館で行われた。明大からは2人の選手が出場し、大観衆の前で堂々の演武を披露した。 ◆5・27 第60回全日本合気道…

新入生歓迎コンパが開催 OB・OG集結で話に花が咲く/明大合気道部新入生歓迎コンパ
5月20日、明大合気道部新入生歓迎コンパが開催された。合計5名の新入生と現役部員3名の他に、合気道部のために力を尽くした師範やOB・OGも出席し、会場は終始にぎやかな雰囲気だった…

聖地・武道館で演武披露 全国から合気道家が集う/全国学生演武大会
1年間の総決算となる全国学生演武大会。全国から71団体の代表者約400人の選手が日本武道館に集結し、明大からは4人が出場。数多くの技を披露し、日頃の鍛錬の成果を発揮した。&nbs…

3年ぶり武道館での開催 聖地で堂々の演武披露/全日本合気道演武大会
昨年度までは新型コロナウイルスのため地方会場での開催だったが今年度は武道の聖地、日本武道館での開催となった。無観客開催となったものの会場は出場者の熱気に包まれていた。明大からは2…
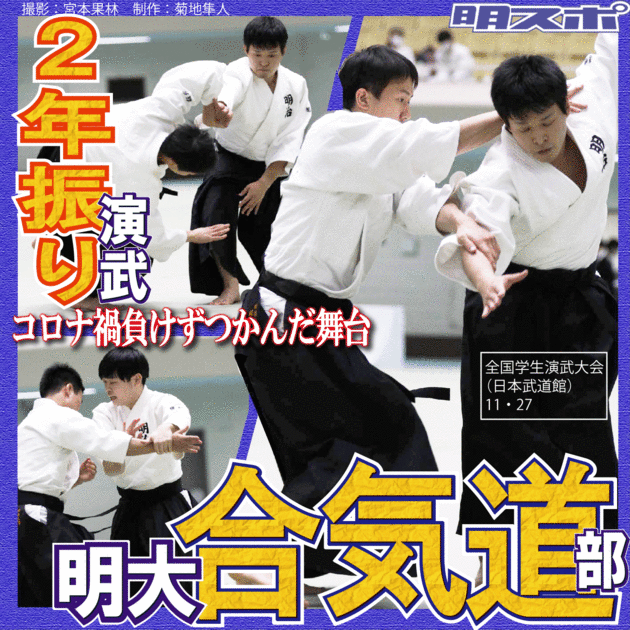
2年ぶりの開催 堂々たる演武を披露/全国学生演武大会
2年ぶりの開催となった。コロナ禍で大会が立て続けに中止となっていたが今年度ついに開催され、明大からは4年生4人が出場。全国津々浦々から集まった学生が日頃の鍛錬の成果を披露した。&…
集大成の演武 心身の鍛錬の成果を披露/全日本演武大会
年に1度の大舞台がやってきた。令和改元後初となった今年度の全日本演武大会。武道の聖地・日本武道館で、日頃の鍛錬の成果を堂々と披露した。 ◆5・25 第57回全日本演武…

全国の大舞台 新体制で鍛錬の成果を発揮/全国学生演武大会
全国から武道の聖地・日本武道館に学生が集結した。学生が主役となる今大会で、明大からは落合昭光主将(法3=明大中野)ら20名が出場。日頃の鍛錬の姿を、堂々と披露した。 …
武道の聖地で堂々の演武 4年生の最後の舞台に下級生も花を添える/全日本演武大会
◆5・26 第56回全日本演武大会(日本武道館)▼演武者 川岸、河守田、橋本、山田寛、田中、小高、落合、梶間、鈴木駿、鈴木優、永友、新井、石井、宗像、山田彩、山中、加藤…
国内最高峰の晴れ舞台 全国の合気道家と共に鍛錬の成果を発揮/全日本演武大会
臆せず修練の成果を披露した。昭和35年からの長い歴史を持つ全日本演武大会。全国2400カ所にわたる道場から、年代や国籍の垣根を越えた約8000人の合気道家が日本武道館に一堂に会し…




